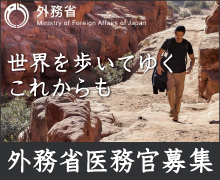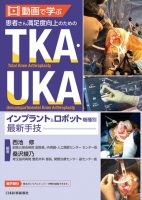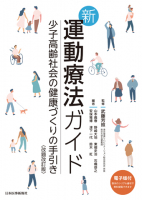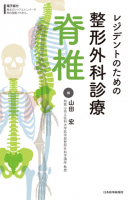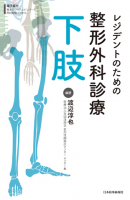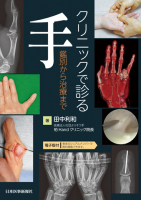jmedmook
お知らせ
主体性をひきだすリハビリテーション 教科書をぬりかえた障害の人々
リハビリ援助が生む新たな生活の構築と、驚くべき機能改善
| 著: | 長谷川幹(三軒茶屋リハビリテーションクリニック院長) |
|---|---|
| 判型: | B5判 |
| 頁数: | 344頁 |
| 装丁: | 単色 |
| 発行日: | 2009年03月15日 |
| ISBN: | 978-4-7849-6195-5 |
| 版数: | 第1版 |
| 付録: | - |
■パーキンソン病、脳梗塞、脳出血、くも膜下出血、脳外傷、関節リウマチ、乳がんの脊椎転移、大腿骨頸部骨折など、障害をもった方々、病とともに高齢で機能が低下した方々が、その家族、医師、理学療法士、言語治療士、看護師などの医療職や福祉職の援助をもとに新たな生活の構築を行い、時間をかけて、医療者の予想を超えた機能改善を示した例を提示します。
■何が転機になったのか?どう工夫したのか?在宅でできたのか?21例のインタビューが熱く語ります。
| 診療科: | 整形外科 | 整形外科 |
|---|---|---|
| リハビリテーション科 | リハビリテーション科 |
目次
解説編
1.在宅障害者・高齢者の現状
2.在宅障害者・高齢者への援助の視点
3.様々な病気の症状
4.これまでの実践活動
事例編
1.パーキンソン病 教科書をぬりかえた例
2.多発性脳梗塞,硬膜下血腫 娘の食事の工夫・介護うつを乗り越えて
3.脳梗塞,重度な左半側空間無視,左片麻痺 5年かけて介助歩行まで可能に
4.脳梗塞,重~中度の失語症,右片麻痺 海外旅行が転機となり展開
5.脳梗塞,右片麻痺 魚料理,裁縫,美容師を
6.96歳で脳出血(視床) 少しずつ回復
7.高齢で脳出血,左大腿骨顆上骨折,右大腿骨頸部骨折,左上腕骨骨折
8.脳出血,重度の失語症,右片麻痺 旅行をきっかけに前向きな姿勢に
9.脳出血(右片麻痺・失語症) 就職,その後右大腿骨頸部骨折を克服
10.脳出血(左片麻痺),左大腿骨頸部骨折 ゴルフに挑戦
11.脳出血(視床),左片麻痺 復職,国際ボランティア活動
12.脳出血,右片麻痺 テイラーに復活
13.脳幹出血,右片麻痺 歩いて歩いて,自分でやってみよう
14.くも膜下出血による重度な自発性低下,失語症,右片麻痺の事例 介護は戦い
15.重度の脳外傷 国際ボランティアと1人暮らし
16.30年前に診た頸髄損傷の方と会って
17.乳がんの脊椎転移による両下肢麻痺 長期間の筋力トレーニングで外出歩行
18.関節リウマチ・第6胸椎圧迫骨折(両下肢麻痺) 数年かけて歩行が可能に
19.若年性関節リウマチ 障害者の自立支援活動で活躍
20.80歳代で大腿骨頸部骨折後に訓練 筋力が改善し,旅行まで可能に
21.脳出血 看護師復職・大学へも
インタビューを終えて
あとがき
序文
26年間のリハビリテーションの仕事を通して、障害のある方、高齢の方など様々な方々とお付き合いさせていただきました。これまで「障害者は暗い」「高齢者は『年だから』機能が低下するのが当たり前」などと否定的な面が強調されてきたように思います。そのため、本人、家族および医療者も先が見えず、あきらめの境地から潜在的な能力を見出してその改善に取り組まず、そのままの状態あるいは低下する状況に陥ってしまうことが少なくありません。その結果、「寝たきり」というぞっとするような言葉が蔓延することになります。
また、60歳代の脳卒中の方で歩行のときに足を引きずる程度の麻痺でしたが、「元に戻そう」と一生懸命筋力トレーニングをしたため麻痺した下肢に痛みが出て室内歩行が困難になった際、当面痛みをとるためトレーニングを止めるよう説明しましたが、約半年間止めませんでした。後日、その理由を尋ねると、「もっとよくしたかったことと、止めると『寝たきり』になるのが怖かったから」と答えられ、外出歩行ができるレベルでもそのように思うのかと衝撃を受けました。そのとき、「寝たきり」を死語にしなくてはならないと強く思いました。
さて、リハビリテーションは障害や高齢によりそれまでの生活の変更を余儀なくされ、混乱から新たな生活の構築に向けた援助をすることであると考えて活動してきました。そういう中で、今までの教科書に書かれていた以上の、我々医療者の予想を超えた能力改善を図り、豊かな生活を送っている人たちが出現しています。このような人々は様々な工夫を行っており、我々にとっては教わることが多いのも事実です。その意味から、障害、高齢の方々は医療者から医療提供を受ける立場にとどまらず、生活のありよう、生活の工夫などを通じて医療者へ情報を提供するという双方向の関係になっています(図)。また、生活には個別性があり、障害にも個別性があることを考えれば、その工夫も個別性があると、改めて考えさせられました。
世田谷区で26年間活動していると、発病から10年以上経過した障害の方々が多くなり、60歳代で発病した人は70歳代になり、80歳代に発病した人は90歳代になり、家族も10年歳をとることにより老老介護が顕著になり、ご本人の加齢による機能低下、介護者の蓄積された疲労など新たな問題が発生し、この対策も考えていかなければならない時期にもきています。
ところで、障害、高齢の方々に「いきいきとした生活を」とよく医療職、福祉職は言いますが、普段我々は自分の生活を語るときに「いきいきとした」という表現を使うでしょうか。特に輝いた行動をしたときくらいにしか使わない特殊な表現ではないでしょうか。障害を持っても「楽しいひと時が持てる」「自分らしい生活ができる」「豊かな生活ができる」くらいではないでしょうか。ここで重要なのは「○○できる」という肯定的な表現に注目すべきであり、否定的な話が多い障害を肯定的な方向への転換を図ることが重要であると示唆されます。
著者は障害を持っても7?8割くらいは工夫と周囲の援助で様々なことができると思いますが、この「できる」という知識(情報)も持ち、さらに入院中からできるだけ早く肯定的な情報を得る環境をつくることが医療、保健、福祉の関係者にとって重要な課題ではないかと考えます。
そのため、これまでお付き合いいただいた障害のある方々に登場していただき、その機運を高めることも本書の目的のひとつであります。
そこで、様々な障害のある方々、高齢の方々に経過報告とともにご本人、ご家族のインタビューを通じて、これまでの苦労、工夫、得たものなどを語っていただきました。ご本人、ご家族はよく「素人だけど…」と言われますが、素人ゆえの感性でとらえる内容が参考になることが少なくありません。
医療保健福祉関係者、および現在苦労されている障害のある方、高齢の方、ご家族など、様々の方々にいくらかでも参考になれば幸いです。
2009年1月
長谷川 幹
レビュー
【書評】著者の何物にもブレない信念が伝わってくるすばらしい1冊
脳卒中によって右片マヒになった患者が、美容師として復帰したいと思う。他院では、歩行困難と診断される。本人の夢を著者は否定しない。著者は、歩行可能と診断する。4年後、奇跡が起きる。
リハビリテーション医の著者が、本人とその夫に4年の間の心の動きを聞きとる。これがすごい。これが役に立つ。他に類のない本だ。
簡単にはリハビリが進んでいないことが分かる。長い目で患者を見ている。患者本人の主体性を引き出すことで、次々に問題が解決されていく。
脳出血を乗り越えて、国際ボランティア活動をする人。乳がんの脊椎転移により、両下肢がマヒするが、長期間の筋力トレーニングで外出ができるようになっていく人。そんな、すごい患者さんたち21人が登場する。
実は著者は、ぼくの大学時代の同級生である。二人の落ちこぼれは仲がよかった。
今、著者は、桜新町リハビリテーションクリニックという、リハビリ専門のクリニックを開業している。世田谷の人に会うと、長谷川くんの話がよく出る。みんなが尊敬しているのがよく分かる。自転車に乗って、訪問リハビリに出かけていく長谷川くんの姿は、地域の人によく知られているらしい。学生時代からいつも原則的な人だった。弱い人に優しい人だった。ブレない人だった。
自分の奥さんが脳出血を起こし、失語症になる。ここでも著者は、他の患者さんと同じように接する。諦めないのだ。完全片マヒから看護師として職場復帰する。本人はもちろん、妻のお母さん、息子、娘などに、その時々の思いを聞きとっている。感動した。著者が一貫して、なんとかなると信じていてブレないのがいい。奥さんは職場復帰しただけでなく、その後、夜間大学へ通う。今は、ある大学病院の幹部看護師の要職をつとめている。
どんな状況になっても、本物の社会復帰ができる可能性があることが、よく分かる。
どこにもない本である。是非、読んでほしい。