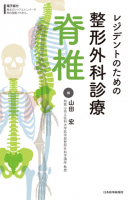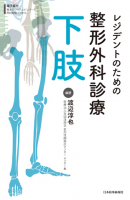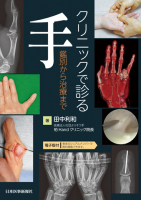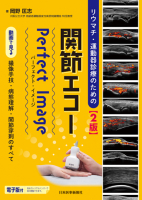お知らせ
疲労骨折[私の治療]

以前は長距離走選手などにおいて,継続的な負担が骨にストレスとして蓄積し,骨折に至ると考えられていた。しかし近年では,利用可能エネルギー不足,つまり摂取エネルギーに対して運動による消費エネルギーが過剰になることで,骨の脆弱化をきたし,骨折に至ると考えられるようになっている1)2)。
▶診断のポイント
【症状】
骨折のため主訴は痛みになる。最も多く疲労骨折を生じるのは下肢骨で,中でも中足骨が特に多いため,足背などに強い痛みを訴える場合には疲労骨折を念頭に置く。腰椎分離症も疲労骨折の一種であるが,この場合は腰痛を主訴とする。年齢は小児から成人まで幅広く,練習量が多い選手に多く発症するので,問診も重要である。女性アスリートの場合は,高率に無月経などの月経障害をきたしていることがあるため3),女性の場合は月経障害の有無も問診する。

【検査所見】
疼痛部に対する単純X線検査が第一選択であるが,単純X線検査では骨折線を確認できないことも少なくない。単純X線検査では骨折を確認できなくても,疼痛が強く,問診で疲労骨折が疑われる場合は,適宜,CTやエコー,MRI検査を追加する。特にMRIによる骨髄浮腫の検出が感度・特異度とも高く,診断能力が高い。腰椎分離症は,両側性の場合は腰椎すべり症や前後屈撮影による不安定性を単純X線検査で確認することで診断できるが,やはりMRIが有用である。

残り1,482文字あります
会員登録頂くことで利用範囲が広がります。 » 会員登録する