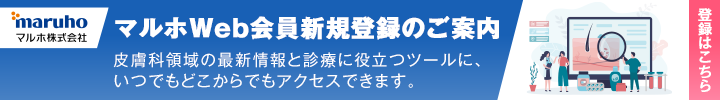×
絞り込み:
124件
カテゴリー
診療科
コーナー
解説文、目次
シリーズ