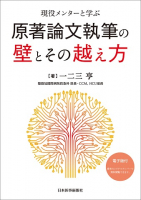お知らせ
HFpEFの診断と治療[J-CLEAR通信(179)]

1 はじめに
心不全の発生率は高齢になればなるほど高くなる。高齢化が進行するわが国では患者数の増加が予想され,「心不全パンデミック」と呼ばれている1)。左室駆出率(left ventricular ejection fraction:LVEF)の保持された心不全(heart failure with preserved ejection fraction:HFpEF)は,LVEF 50%以上と定義されている。
しかし,HFpEFはLVEFの低下した心不全(heart failure with reduced ejection fraction:HFrEF,LVEF 40%以下)と比べても,心血管死や心不全による再入院のリスクは同等である。これらの間にLVEFが軽度低下した心不全(heart failure with mildly reduced ejection fraction:HFmrEF,41%≦LVEF≦49%)が定義されているが,その特徴にはかなりのオーバーラップがある。米国のデータでHFpEFは,年1.4回程度の入院と年15%程度の死亡を引き起こし2),がんよりもむしろ予後不良である。

HFpEF,HFrEFどちらも主死因は心血管疾患であるが,HFpEFでは非心血管疾患死も多い3)。先進国で心不全罹患率は成人の1~2%と推定されているが,オランダでは2型糖尿病で心不全と診断されていない60歳以上の27.7%に心不全が見つかり,22.9%はHFpEFであった4)。また,一般人の心エコー研究のメタ解析では,65歳以上における心不全の有病率は11.8%で,その4分の3がHFpEFであった5)。このようにHFpEFが最も一般的な心不全となりつつある。
2 HFpEFの病態生理
HFpEFでは左室拡張能の障害により拡張期充満圧が上昇すると,左房圧が上昇して左房のリモデリングが起こる。さらに,肺高血圧症(pulmonary hypertension:PH)が約80%にみられ(PH-HFpEF),死亡率が上昇し,PHはやがて右室収縮障害を起こす。
PHの主体は後毛細血管性(post-capillary PH,2群)であるが,一部は前毛細血管性(pre-capillary PH,1群)を合併した後毛細血管性・前毛細血管性複合型肺高血圧症(combined pre and post-capillary PH)である。PH-HFpEFは,PH-HFrEFよりも頻度が高いが,インスリン抵抗性や炎症が関係するとされる6)。
HFpEFの病態生理は複雑である。HFpEFの定義はLVEFを基準にしているが,単一の疾患とは考えられないぐらい異質な病態の集まりであり,異常部位は多岐にわたる。心臓(心室,心房),肺,肺動脈,右心系,弁,肥満,全身の代謝,骨格筋,腎臓,肝臓の構造や機能の異常などが関係しており,病態生理に関する多くの仮説が出されている。
HFpEF患者のほとんどが高血圧症の既往を有するが,『ACC/AHA高血圧治療ガイドライン』7)に則って高血圧を治療することで,HFpEFの発症を2~8年にわたり40%程度低下できる8)9)。このエビデンスから,高血圧の不十分な治療がHFpEFの原因のひとつであり,HFpEF患者は高血圧性の左室肥大と病的な心筋の線維化を有すると予想された。しかし,左室肥大の基準に合致するのはHFpEFの半数以下であり,心筋の線維化の増大は有意ではあるものの高度ではなかった。
筋原線維(タイチン)のスティフネスや心筋の線維化が拡張機能障害に関係することから,他の仮説,すなわち「多システム変化仮説」が生まれた。COPD,腎障害,糖尿病などの炎症惹起性の併存症が,心筋内微小血管の内皮細胞の炎症から酸化ストレスの亢進,NO-可溶性グアニル酸シクラーゼ-PKGシグナルの低下,機能不全に陥った蛋白(小胞体ストレス等)のクリアランス障害10),心筋の構造や機能の障害をきたし,冠動脈の微小血管の機能不全に至るというものである11)。
実際,HFpEF患者ではcGMP低下がみられる。また,前白血病後天性遺伝的変異をもつ血液幹細胞のクローン増殖であるCHIPは,70歳以上の約10%に起こる加齢関連疾患であるが,CHIPバリアント(TET2)と炎症がHFpEFに関係することが報告された12)。さらに,糖尿病や肥満で心外膜脂肪組織が増加すると,そこからadipocytokinesが分泌され,心筋の炎症や線維化を起こすという仮説も出されている。
しかし,HFpEFに対する抗炎症薬の効果は検証されておらず,NOシグナルを改善する薬の臨床試験の結果は否定的であった。HFpEFには多くの経路が関係し,それぞれの経路に応じた治療が必要であるという考えに基づいて,HFpEFのheterogeneityや併存症に注目したフェノタイプ研究が行われている。