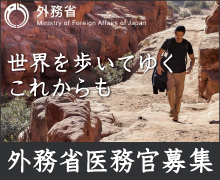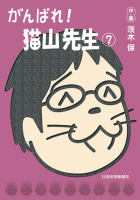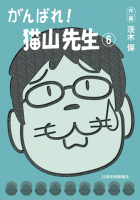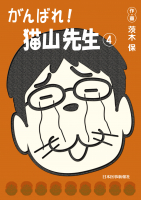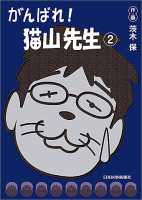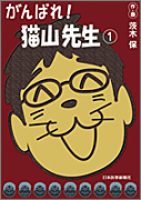お知らせ
つれづれなる感想とススメ~循環器専門医が『現場の疑問に答えるCPAP療法Q&A』を読んだら~
諸兄は,「CPAP療法士」という資格をご存知だろうか。“シーパップ”「CPAP」は持続陽圧呼吸[療法](continuous positive airway pressure)のことで,こちらは大半の方がご存知かもしれない。
国家または法的資格ではないが,(一般社団法人)日本睡眠総合検診協会が認定しているものである。約1カ月の間,睡眠時無呼吸(症候群)に関連するオンライン講座を受講し,最終試験に合格すると取得できるというスタイルだ。
【参考】
http://seminar.suiminken.or.jp/?page_id=2817
当方も,ひょんなことから同資格をゲットする必要に迫られた。セミナー講師の顔ぶれは様々で,“睡眠科”に関与する医師,歯科医師,臨床検査技師,看護師などである。それぞれの診療科・職種の視点による指南は,実に興味深い。研究会でも学会でも,玉石混交の“細切れ”情報が氾濫する中,最後まで“寝落ち”しないレクチャーには昨今なかなか当たらないのに・・・。
CPAP療法による治療ターゲットとなるのは,睡眠時無呼吸(症候群)で,世間では“サス”(SAS)*1)と呼ばれることが多い疾患である。広くは睡眠関連呼吸異常症の1つに分類され,中でも“オーエスエー”(OSA)――「閉塞性」(obstructive)とされるタイプが,CPAP好適応になる。
*1)最近では,専門家の中では,SASという表現はあまり使われなくなっているらしい。ただ,親しみやすさ,“知名度”的にはバツグンの本表現を,今回の散文ではあえて用いることにした。
SAS診療には,内科(一般,循環器,呼吸器ほか),耳鼻咽喉科,精神科,歯科・口腔外科など,多くの医師,歯科医師が関与する。
当方は循環器および臨床検査を専門とする医師だ。ともにSASと深い関係のある領域で,前者は臨床そのもの,後者は主に診断機器を介した側面であると思われる。
一時期,SASを研究テーマの1つにも据えたことがあり,マニアックな部分まで突き詰めていたように思う。また,だいぶ以前から,実臨床でも,かなりの数のSAS患者を,それなりに診察してきた気もしていた。“嫌いじゃない”――ストレートな表現を避ければ,自身のSASに対する印象はこれだ。さらに,前述のCPAP療法士であることも,さりげなく誇りに感じていたのかもしれない。そして,当方 のみならず,現在,SASとまったく無関係に循環器専門医として働くのは無理だろう。
ただ,日本医事新報社から御献本いただいた,谷口充孝氏による『現場の疑問に答えるCPAP療法Q&A』を読み終えた後,いかに自身が“にわか”か思い知らされた。それくらい多くの新鮮な学びが詰まっていたのだ。
読者諸兄におかれては,浅学な当方とは状況が違うのかもしれないが,たとえば,
- SASスクリーニングには,エプワース眠気尺度*2)だけで良い?
- HSATって何のこと?
- SASはAHIの数値“だけ”で診断できる?
- AHIとREIの違いは?
- AHIと3%ODIが乖離したときに考えること,対応は?
- PSGによるCPAP適応は“重症”(AHI 30/hr以上)の基準と一致する?
- CPAPアドヒアランスは4時間を境にした評価で十分?
- CPAPマスクの3つのタイプの使い分け,それぞれの長所・短所は?
- 「こんな治療は苦しくて続けられない」という患者にはどう対応する?
- CPAPの圧タイトレーションは全例に必要?
- 未治療の重症SAS患者の職業運転を禁止できる?
*2)Epworth Sleepiness Scale(ESS)
という質問にすべて正しく答えられるだろうか。もし,1つでもわからない,または,曖昧であれば,本書を手に取る価値がきっとあるはずだ。
著者の解説は実に丁寧だ。以前にT社の担当者から頂戴し,とてもわかりやすいなぁと感じた解説冊子(医療資料“パンフレット”)の監修者その人の著述であると気づいたときに,妙に納得してしまった。
同書の全体的な構成は以下のようになっている(全27頁)。
【1】はじめに
【2】SASの基礎知識
【3】SASの臨床症状とリスク
【4】SASの診断とCPAP療法Q&A
【5】練習問題
はじめの3つは“イントロ”的な内容だ。主にSAS(特にOSA)の基本病態や症状,合併することの多い疾患について解説されている。症状に関しては,日中の眠気や不眠,いびきに加えて,(起床時)頭痛や夜間頻尿,そしてED(勃起不全)とも関連することは,診察時の問診に必ず付け加えなくてはいけないと感じた。
また,高血圧や冠動脈疾患,心房細動など,循環器医が普段から接することが多い疾患以外に,うつ病や認知症,そして一部のがんなどにも関連する可能性に関する言及も新鮮であった。
【4】は,本書のキモとも言える,SASの診断と治療に関する12個のQ&Aからなる。スクリーニングとして,STOP-Bangテストや,気管内挿管のしにくさを評価するMallampati(マランパチ)分類が使える点は初耳だった。実際の診断に関しては,いわゆる“(精密)PSG”の専門的な話ではなく,多くの医師が評価に用いる“簡易PSG”*3)を中心に解説してくれており,これも非常にありがたく感じた点だ。
*3)最近では,HSAT(home sleep apnea test)とも呼ばれる。
今まで「AHI」という表現を気軽に使ってしまっていたが,より正確には,「REI」(respiratory event index)と呼ぶべきという,米国睡眠医学会(AASM)の推奨についても,明快な解説がされている。そういうことだったのか!
治療法の選択に際しては,重症度と,保険適応(診療報酬)上のAHI数値が若干異なること,そして,行った検査が(精密)PSGかHSATなのかにも改めて注意を払うべきことが強調されている。引用されているガイドラインからの抜粋フローチャートは復習になった。フムフム,ここは特に明快だ。
さらに,続くQ5~Q8で“真打ち”登場である。CPAPの導入時の説明,圧設定やマスクの選択と各々の特徴がわかりやすい写真・画像とともに提示されており,秀逸である。明日,いや,今日すぐにでも生かせそうだ。
Q9では,実際のSAS外来で患者と供覧する“CPAPレポート”についての注目点を指摘してくれている。そうそう,“SAS外来”では,このレポートを迅速かつ的確に読み解いて診療しないといけない。“ココ見ろ”的なピンポイントな指導は,われわれの作業効率を上げてくれる。
使用率(時間)やリーク,“95%圧力”の解釈は,おおむね自身の考えとも一致し,安心した。Q10は,“コンプライアンス”(より適切にはアドヒアランスと言うべきか)に関連する患者の訴えへの対応法が列挙されており,特に実践的に感じた。CPAP療法がどれだけエビデンスを有していようとも,“使えてナンボ”であることを再認識させるものだ。圧迫感・息苦しさ,鼻閉や腹部膨満など,“あるある”への対処に関して,具体的なアドバイスが光る。なお代表的な「4時間」以外に「6時間」以上という基準もあることは正直知らなかった。鼻閉はすべて“耳鼻科任せ”にしていた自身のスタイルは,今後変更しなくてはならないようだ。
本書は,全体にわたって,SASに関する“Tips & Pitfalls”が随所にちりばめられている。全部で1~2時間,ここまで食い入るように読む,を実践できた書籍も最近,珍しい。ここまで理解できたら,最後の練習問題は“瞬殺”であり,自身の成長も感じつつ,爽やかな気持ちで読み終えることができた。
最後に,ほんの少しだけ残念だった点がなくはない。
個人的には,当方が専門とする心血管疾患の治療や管理についての記事が,もう少し充実していると尚良かったように思う。治療抵抗性高血圧を有する患者への具体的対処法,ほかに心房細動アブレーション前後でのSASの評価・管理法ほか,エビデンスとなるキー論文とともに紹介してくれたらありがたかった。あっ,元来の“欲張り”な性格が出すぎたかも・・・しれない。
また,パンデミックという言葉が当たり前になりつつある心不全の診療に日々苦戦しているが,高率に認める“CSA(S)”,すなわち中枢性無呼吸の取り扱いについても詳しく教えて欲しかった。ASV(adaptive servo ventilation)って,本当に“オワコン”なの? ワンチャン,どういう人には“いける”――そんな話も聞きたかった。
この辺は,日本循環器学会のガイドライン(https://www.j-circ.or.jp/cms/wp-content/uploads/2023/03/JCS2023_kasai.pdf)も一読しておくのが良いだろうか。自身では,こうしたデータも日々収集しており,何かの機会に是非コラボしたいなぁと思った。
また,個人的には“盟友”である「心電図」との兼ね合い,特に簡易検査への活用面を少しだけ取り上げて欲しかった。“CVHR”は1つのキーワードで,他にも心電図の“裾野”を感じることのできる分野の1つである。
そして,最後にもう一点。本5月にNHKでも放送され話題となった,舌下神経電気刺激療法に関する現在と今後の展望があったら,“満点”のストーリーだったかもしれない。
SAS診療に関わる者にとって,本書は間違いなくアタリだろう。“大”が付くやもしれない。そう確信する。評者も含め,本書がより多くの医療者の目に触れることを切に願って,本稿を閉じたい。