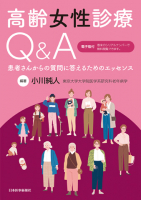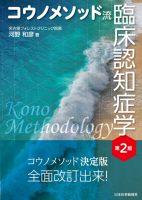お知らせ
【識者の眼】「認知症は予防すべきか、共生すべきか」岡村 毅
『共生社会の実現を推進するための認知症基本法』が2024年1月に施行され、同年12月に『認知症施策推進基本計画』が決定され、社会が一気に動きはじめている。
市井の人々が「認知症にはなりたくないなあ」というのは自然な感情だ。ご承知のように、〇〇運動がよいとか、某オイルがよいとか、いろいろな流行が出ては消えたものだ。これはしかたのないことだろう。

しかし、研究者の間でも、認知症研究といえば認知症予防研究しかなかった。予防のためのプログラム開発も盛んだったが、科学的には眉唾物も多かった。
精神科医の立場からは、これはとても危険だと指摘したい。そもそも年を取ればどんなに健康的な生活をしていても、認知症になるときはなる。予防教室に行っていた方が、認知症になったとたんに「あなたは認知症だからもう来ないで」と言われる、あるいは自ら「ああ、私は認知症になってしまった、大失敗だ」と思って閉じこもる、という悲劇がしばしば起きる。かつては認知症と診断されて途端に、医師が本人の話を聞かなくなり、家族とだけ話すようになった、といったこともあった。予防推しの人は善意でやっているのだろうが、「結果的に」排除の思想と背中合わせなのだ。
しかし、2009年の英国の「認知症とともに良き生活(人生)を送る」(認知症国家戦略)や、2015年の日本の「認知症の人の意思が尊重され、できる限り住み慣れた地域のよい環境で自分らしく暮らし続ける」(新オレンジプラン)などが流れを変えた。2019年の認知症施策推進大綱では、当初、認知症の人を〇人減らします、と書いたところ大ブーイングにあい、予防とは「認知症になるのを遅らせる」「認知症になっても進行を緩やかにする」という意味です、という注釈がついた。つまり、「絶対ならない」という旧来の予防概念が解体された。
このように書くと「認知症にはなりたくないと思うことの何が悪いの」と思われるかもしれない。しかし、政府が「認知症の人を減らします」と宣言してしまうと、認知症の人はどう思うだろうか。自分たちはいないほうがよいのかな、と思うのではないか? これは人権と想像力の問題だ。
さらに説明しよう。私は学生時代、ダウン症の子どもなどに水泳を教えるNPOをやっていた。ダウン症の子どもは朗らかで、親子仲のよい家庭が多く、結構楽しい活動だった。そこで私が「研究してダウン症の子どもが生まれないようにします!」と言ったら、皆どう思うだろうか? 「そういう言い方はひどい」と思うだろう。
もうおわかりだろう。私は認知症予防を否定しているのではない。予防とは「認知症には絶対にならない」ということではなく、「認知症になるのを遅らせる」であるべきで、認知症になっても支える姿勢(共生)がなければ排除になるよ、と言っている。これまでは予防の研究ばかりだったから、共生の研究のエビデンスはほとんどないというのが実態である。私たちは全力で遅れを取り戻さねばならないのだ。
岡村 毅(東京都健康長寿医療センター研究所研究副部長)[認知症][予防][共生]