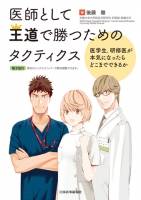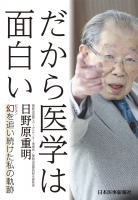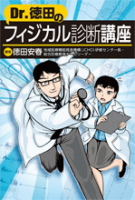お知らせ
【識者の眼】「迷走しているように見える博士課程学生支援事業」八谷 寛
報道などでも広く知られたように、国立研究開発法人科学技術振興機構(JST)の博士後期課程学生支援の対象(生活費相当額の支援)から、外国人留学生を排除することが決定した。JSTのサイトには理事長名で「『次世代研究者挑戦的研究プログラム(SPRING)』による博士後期課程学生支援制度の見直しについて」とする記事が掲載された。
その記事の中で、「本制度は、アカデミアの有志研究者の提言を受け、日本の将来を担う博士後期課程学生を力強く支援することを目的に構想されました。制度創設にあたっては、学術界のみならず、産業界や国会、国会議員の方々の間でも活発な議論とご支援があったと認識しております。しかしながら、その趣旨が制度化の過程で十分に明示されなかったことから、事業開始後、日本人以外の学生にも支援資金が広く配分される運用となっておりました。今回の方針は、制度本来の目的に立ち返り、その運用を当初の趣旨に即した形に是正するものです」と述べられている。

日本人以外の学生にも、支援資金が広く配分されたことは事実だろう。しかし、それが本当に「日本の将来を担う博士後期課程学生を力強く支援」することに反しているかについては述べられておらず、釈然としない。
現制度は、JSTに申請して採択された全国60の大学で運用されている。運用方法は大学によって異なる面もあるが、「1人の選抜学生への支給額は、生活費相当額と研究費をあわせ220万円/年を下回らないこととする」などのルールが設けられている。学生の選抜にあたっては、本人が、指導的立場にある教授・准教授などの指導のもと立てた研究計画と、それら研究者による推薦書が、同じ大学の別分野の研究者による評価(基本的に相対評価)によって決定される。選考委員となる研究者には、本制度が「日本の将来を担う博士後期課程学生を力強く支援」するもの、つまり、日本人学生は、基本的には優先的に支援されるべきという趣旨が共有されていると理解している。換言すれば、外国人学生が日本人学生の枠を奪っているというより、日本人学生の応募がそこまで多くないのが現状ではないのか。
そもそも大学院重点化によって増えた大学院の定員を、日本人だけで埋めることや、研究の現場を日本人だけでまかなっていくことは現実的ではない。外国人留学生も日本の将来を担う重要なプレーヤーであり、その重みは増している。日本人の博士課程進学者を増やすことは重要だが、大学院での支援だけでは遅過ぎるし、範囲が狭すぎる。
また、文部科学省がJSTを通して実施する国際卓越研究大学制度等でも、各大学はこぞって国外から研究者や大学院生を呼び込むための支援策を打ち出している。本SPRING事業において、日本人と外国人をわけて選考するのであれば、排外主義的な議論に陥ることは避け、制度創設時の趣旨からは少し離れるかもしれないが、これまでの日本人応募者の採択率、外国人応募者の採択率、各大学院に占める外国人留学生者数などを見える化し、国の将来を見据えて、冷静に議論すべきである。
研究者育成支援にしても、反射的あるいは情緒的な決定論理ではなく、大局的な視点が必要ではないだろうか。大学も予算に縛られて、地に足がついた対応がとりにくくなっているように私には映る。
八谷 寛(名古屋大学大学院医学系研究科国際保健医療学・公衆衛生学分野教授)[次世代研究者挑戦的研究プログラム][SPRING]