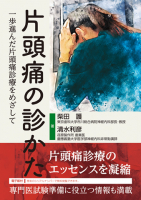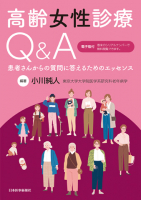jmedmook
お知らせ
jmedmook99 かかりつけ医が知っておきたい 新時代の認知症サポート
地域で認知症患者を診療・ケアするために!
| 編: | 遠藤英俊(いのくちファミリークリニック院長,聖路加国際大学臨床教授) |
|---|---|
| 判型: | B5判 |
| 頁数: | 176頁 |
| 装丁: | カラー |
| 発行日: | 2025年08月25日 |
| ISBN: | 978-4-7849-6699-8 |
| 付録: | 無料の電子版が付属(巻末のシリアルコードを登録すると、本書の全ページを閲覧できます) |
◆ 認知症1000万人時代の到来に伴い、今後は「かかりつけ医」や「認知症サポート医」が果たす役割がきわめて重要になると言われています。
◆ 難しい症例は専門医に委ねるとしても、かかりつけ医が認知症の診断において困ることは多く、専門医が診断した患者の日常診療を受け持つ場合もまた同様です。
◆ 本書ではかかりつけ医、あるいは認知症サポート医として地域で認知症患者を診療・ケアするために必要な知識に加え、様々な社会資源の活かし方など、知っておきたいトピックをわかりやすく解説しています。
◆ 地域で活躍する認知症サポート医、かかりつけ医の先生の現場で役に立つ1冊です!
目次
Chap1 認知症の基礎を理解する
1 かかりつけ医による認知症の理解
2 認知症とともに生きる人,家族が集まる診療所
3 かかりつけ医と認知症
4 軽度認知障害(MCI)の現状と課題
5 かかりつけ医がMCIにどう対応するか
6 日本の認知症有病率はなぜ低下したのか
7 アルツハイマー型認知症の診断
8 アルツハイマー病特化型診療所
9 レカネマブの適正使用のための,診療連携
10 レカネマブの効果と限界
11 認知症の神経心理学的検査および評価尺度
12 認知症の画像診断(アミロイドPETを含む)
13 認知症のバイオマーカー検査
14 認知症の行動・心理症状(BPSD)
15 かかりつけ医のBPSD治療
16 BPSDへの対応
Chap2 疾患別認知症を理解する
17 レビー小体型認知症の診療
18 血管性認知症の診療
19 前頭側頭型認知症の診療
20 慢性硬膜下血腫の診療
21 特発性正常圧水頭症(iNPH)
22 うつ病と認知症の鑑別方法
23 てんかんによる認知症症状
Chap3 認知症の医療とケアを理解する
24 認知症の家族支援
25 認知症カフェ
26 かかりつけ医と認知症サポート医の役割
27 初期集中支援チームとの連携と役割
28 かかりつけ医と認知症疾患医療センターの連携
29 認知症の非薬物療法
30 より良い認知症ケアを求めて
31 認知症予防:危険因子と予防
32 認知症短期集中リハビリテーション
33 入院・入所の基準
34 介護施設入所者への対応
35 精神科医や精神病院との連携
36 認知症の終末期医療
37 高齢者虐待防止と身体拘束廃止への取り組み
38 認知症基本法と大綱の理解
39 介護保険制度と介護サービスの利用
40 高齢者運転と認知症─高齢者運転免許の現状と課題
序文
巻頭言
本書ではかかりつけ医の認知症診療のために,各分野のエキスパートにお願いし,明日から役立つ最新の知識をまとめた。是非日常診療に役立てて頂きたい。
2022年に行われた二宮らによる最新の認知症有病率調査では,認知症の有病率は12.3%であった。2012年の厚生労働省の認知症有病率調査の報告では15%となっており,その結果を比較すると認知症有病率は2.7%の低下を示している。しかし,軽度認知障害(mild cognitive impairment;MCI)の有病率は13.0%から15.5%に増加した。つまり認知症は大きく減少しているとは言えず,主治医意見書の記載も求められるなど,かかりつけ医にとり避けて通れない疾患となっている。
いまや,かかりつけ医は認知症診療の入り口であり,要となっている。最近では各地でレカネマブやドナネマブの投与を前提としたMCI外来開設をよく耳にする。しかしながら患者,市民への周知はまだ十分でなく,自身や家族がMCIと認識して,進んで受診する人はまだ稀であると思われるため,当面「認知症ドック」を広める必要があろう。しかしながら地域のパイロットとして,対象者を見つけ,紹介するなどかかりつけ医の役割は大きく,今後MCI外来に対してかかりつけ医が紹介することが多くなるであろう。また,都道府県格差や地域格差も大きく,レカネマブやドナネマブの対象者が適切に,どこの都道府県でも標準的治療を受けられる環境が整うことを期待している。
ところで40年前には認知症を痴呆症と言い,検査や治療の対象でなかったが,筆者は長谷川和夫先生の指導で,痴呆症診療とともに老年内科の診療を行ってきた。筆者は長年,国立長寿医療研究センターの「もの忘れセンター外来」において診療と研究を行い,また並行して,厚生省(現・厚生労働省)の介護保険制度の構築のサポートを行ってきた。また,NHKなどのマスコミ出演時には「認知症は誰でもかかりうる疾患である」として,受診の偏見をなくし,受診のハードルを下げる努力をし,一般の人に認知症の理解を進めてきた。さらにはかかりつけ医の認知症対応力向上研修や認知症サポート医研修の立ち上げを行った。多くの医師の研修参加の協力に感謝している。
筆者は定年後の2021年3月に診療所の開設に踏み切った。その理由としては,より地域に密着し,地域で活動するかかりつけ医をめざす,すなわち地域包括ケアを実践すること,在宅医療を実践し,発病から看取りまでの支援ができる医療をめざしたい思いが強かったためである。時に初期集中支援チームと連携したり,運転免許更新のための診断書を記入したりして,患者への貢献の実感をもつことができる。そこへ待ちに待った抗アミロイドβ抗体薬であるレカネマブやドナネマブ,長年必要としてきた「疾患修飾薬」の登場である。これらの治療薬に期待するが,まずは可能な限り,新薬を必要な人に届けたい。
そして,現在考えていることは認知症に関わる地域連携である。認知症疾患医療センターや認知症専門医,認知症サポート医をはじめ,介護施設や介護支援専門医との地域での連携である。かかりつけ医が日常診療でMCI患者を見つけるために,65歳時や70歳時に改訂長谷川式簡易知能評価スケール(Hasegawa's Dementia Scale-Revised;HDS-R)による検査を行い,頭部MRIを依頼し,スクリーニングを行い,海馬の萎縮や脳血流SPECTで後部帯状回の血流低下があれば,直ちにレカネマブやドナネマブの初期投与施設に紹介する連携が必要であろう。しかしながら,投与施設が遠方であったり,金銭面で脱落したりする患者,また治療を受けたくても条件に合わない患者も存在する。そうした方には他の治療方法を紹介するような外来も必要であろう。今後そうした連携や支援体制の構築が必要であり,認知症疾患医療センターに期待しているが,課題が多いセンターもあり,今後はセンターの役割強化と活動条件や役割の見直し,さらにはかかりつけ医の意識改革と機能強化も必要であろう。
物忘れがあればドネペジルを漫然と投与する時代は終焉を迎えた。レカネマブの登場により,認知症診療の革命が起きたと言えるであろう。かかりつけ医の知識と経験のバージョンアップと,地域連携の強化が必要である。そのためには地域の医師会や勉強会の役割は大きく,また認知症のかかりつけ医やサポート医研修テキストの改訂も必要である。
今後はかかりつけ医こそがMCIの外来を行い,連携によるフォローアップ施設となり,認知症診療を地域ごとのチームで構築する必要がある。本書を通じて一人でも多くのかかりつけ医とともに新しい時代を進めていきたい。
2025年7月
いのくちファミリークリニック院長,聖路加国際大学臨床教授
遠藤英俊