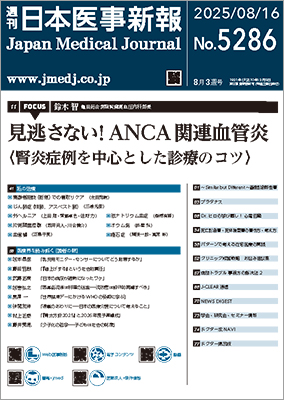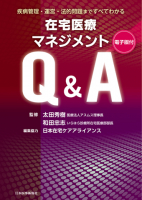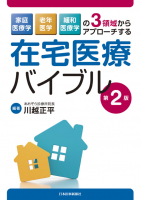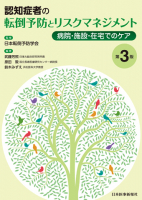お知らせ
ICTを利用した在宅医療[私の治療]
近年,人口動態の著しい変化の中で,医療と介護を必要とする高齢者が急増している。そのため,医療提供体制の整備とともに,限られた数の医師がかかりつけ医の機能を発揮し,それを支える多職種との情報共有手段として,在宅医療分野でのICT(information and communication technology)の活用は不可欠な時代となった。在宅医療におけるICTの活用については,令和6(2024)年度の診療報酬改定でも高く評価されている。今後,医師のオンライン診療〔D to P with NまたはC(doctor to patient with nurse or care worker)〕,急変時・災害時など,ICT活用の場は広がるであろう。今後さらに需要が増す在宅医療において,在宅医療関係者だけでなく,患者本人の意思をつなぐ手立てとしてICTは有用である。
▶制度面の知識
2024年度診療報酬改定の大きな柱となった,在宅医療におけるICTを用いた連携について,在宅医療の場面に即して考える。まず根底に,日常の療養生活支援において,本人のACP(advance care planning)をふまえつつ,日常的に連携する医療機関間,また在宅療養を支える関係機関・施設とICTを用いて情報共有し,さらにカンファレンスができる体制を図ることが肝となる。それを基盤とし,多職種との在宅医療情報連携加算や往診時医療情報連携加算,在宅がん患者緊急時医療情報連携指導料,また介護保険施設等の協力医療機関として協定を締結した施設へ往診を行った場合の介護保険施設等連携往診加算,協力対象施設入所者入院加算等が算定可能となる。そして退院支援の場面においては,先の改定で算定可能となったオンラインカンファレンスへの活用が可能となる。また,終末期の場面においては,ICT活用により日々の患者の病態変化,ACPを含めた本人の気持ちの変化も関係者間で共有することができ,本人の意思に沿ったケアの実践が可能となる。


残り1,254文字あります
会員登録頂くことで利用範囲が広がります。 » 会員登録する