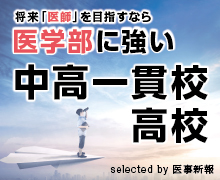お知らせ
【識者の眼】「日本版ホスピタリスト〜国家ブランド力の投影に期待?」田妻 進
田妻 進 (日本病院総合診療医学会理事長、JR広島病院理事長・名誉院長、県立二葉の里病院顧問)
登録日: 2025-05-28
最終更新日: 2025-05-27
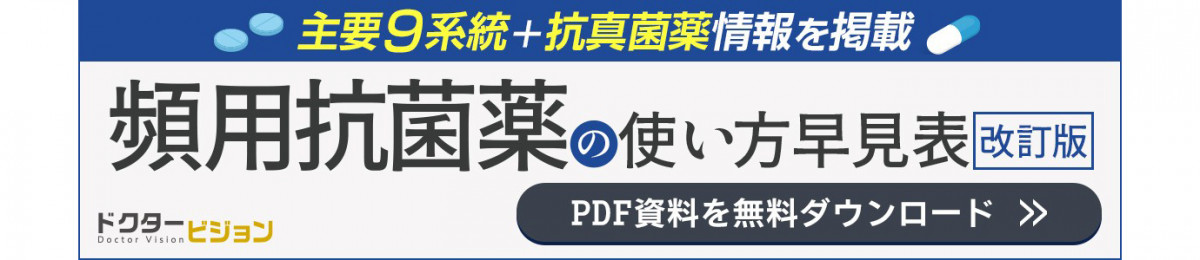
本連載では、VUCA時代における日本の医療制度を支える重要なピースとして、日本版ホスピタリストの登場が期待されることを伝えるとともに、その医師像、プライマリ・ケアの現場でのミッション、そして、育成に際して日本病院総合診療医学会が掲げるコンピテンシー4軸〔臨床(practice)、教育(education)、研究(research)、病院管理(hospital management)〕について情報共有してきました。
その特徴の1つとして、前稿(No.5277)では、hospital managementを取り上げて「医療経営」に係るホスピタリストの位置づけを紹介しましたが、本稿は、国家観の視点で日本版ホスピタリストを考察してみたいと思います。
筆者が米国クリーブランドクリニックでフェローシップを修了した1987年、日本は空前の好景気で、株価、為替レート、債券価格が当時の史上最高値(?)を更新していたと記憶しています。そのため手持ちの米ドルを日本円に換金せず、銀行口座を米国内に残して帰国しました。しかし、その後、バブルが崩壊し、経済大国としてOECD諸国から強い関心を集めてきた日本も長期的な経済成長鈍化に苦しみ、“失われた20年”あるいは“30年の低迷”に苦悩していると言われます。そして今、変動性(volatility)、不確実性(uncertainty)、複雑性(complexity)、あいまい性(ambiguity)からなるVUCAの時代を迎えて、既存の教科書的な発想の踏襲では、山積する新たな課題を克服できないことが危惧され、既成概念にとらわれない志向性が求められています。とりわけ日本の焦燥は深刻と受け止める向きもあり、気がかりなのは筆者だけではないでしょう。
その一方で、先ごろ日本に朗報が届きました。2023年11月、フランスの調査会社アンホルト・イプソスが発表した国家ブランド指数(NBI)で、日本が史上初の首位に立ったのです。NBIは、幅広い人々(観光客、学者、投資家など)を対象に「輸出」「ガバナンス」「文化」「人材」「観光」「移住と投資」のカテゴリで調査するものですが、ドイツ、米国以外で、日本が初めて首位になったのです。その要因として「共感重視の論理」が論じられています。人に寄り添い、気遣い、時には自らを後回しにする利他的行動を優先する道徳心、私たち日本人が長年培ってきた惻隠の情こそが数字に表せない肌感覚として、調査対象者の高い定性的評価に帰結したのではないかと解説されています。1989〜92年に日本がトップランクに君臨しながら、その後に急落した世界競争力ランキングとは対照的な国家観であり、日本の歩みの底流にあるDNAを感慨深く再認識したところです。
さて、日本が認められた国家ブランド力「共感重視」は、臨床医にも共通する姿勢であり、とりわけ総合診療医には意識する場面が多いのではないでしょうか。人工知能が人類の生き残りに必要な解として挙げた『利他的行動と道徳心』も、2000年を遡る孟子の言葉「惻隠の心は仁の端なり」との共感と受け止めることができます。『良質で安心安全な医療』『患者さんに寄り添う医療』『健全な病院運営のもとに提供する医療』を実現するために、わが国の素晴らしい国家ブランド力「共感重視」を投影した、日本版ホスピタリストの活躍に期待しましょう。
田妻 進(日本病院総合診療医学会理事長、JR広島病院理事長・名誉院長、県立二葉の里病院顧問)[地域医療構想][ホスピタリスト]