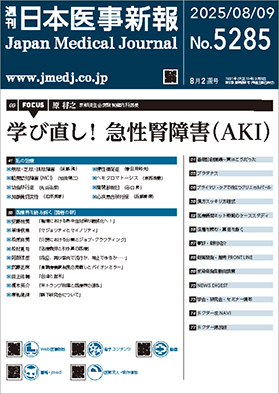お知らせ
僧帽弁閉鎖不全症[私の治療]

僧帽弁閉鎖不全症(mitral regurgitation:MR)は,僧帽弁複合体(弁輪,弁葉,弁尖,腱索,乳頭筋)の器質的異常のほか,左室拡大による心尖部方向への弁尖の偏位(tethering)や左房拡大によっても生じ,前者の場合を器質性(一次性)MR,後者の場合を機能性(二次性)MRと呼ぶ。
慢性MRでは,左室・左房の拡大と左室過収縮により血行動態は代償されるが,重症MRが長期に及ぶと非代償期に移行し,心不全をきたす。腱索断裂などによって急性MRが生じた場合には,左房拡大による代償機転が乏しいため容易に左房圧が上昇し,内科的治療ではコントロール困難な重症心不全をきたす。
▶診断のポイント
息切れや動悸などの症状に加え,汎収縮期逆流性雑音を心尖部に聴取し,僧帽弁逸脱症の場合,前尖の逸脱では左腋窩に,後尖の逸脱では前胸部に放散する。重症MRでは,Ⅲ音ならびに拡張中期ランブル(Carey-Coombs雑音)を聴取する。収縮期クリックは僧帽弁逸脱に特有の所見である。急性MRや心不全合併例では,左房圧上昇に伴い心雑音が減弱する場合もある。心電図における左房負荷,左室高電位,胸部X線における左房拡大に伴う左第2,3弓の突出,気管分岐角の開大を認め,心エコーにて僧帽弁複合体の異常ならびにカラードプラ法における僧帽弁逆流ジェットを認める。volumetric法やproximal isovelocity surface area(PISA)法により,逆流量(regurgitant volume:RV),逆流率(regurgitant fraction:RF),有効逆流弁口面積(effective regurgitant orifice area:EROA)などを求め,定量評価する。
▶私の治療方針・処方の組み立て方
MRが中等度以下で症状がない場合には,定期的な心エコー検査による経過観察が中心となる。心不全を合併した際には利尿薬などの薬物療法を開始するが,早期に外科的治療介入を考慮する。急性MRの場合,内科的治療による血行動態の安定化を図ることは困難であり,緊急手術を考慮する。

残り1,724文字あります
会員登録頂くことで利用範囲が広がります。 » 会員登録する