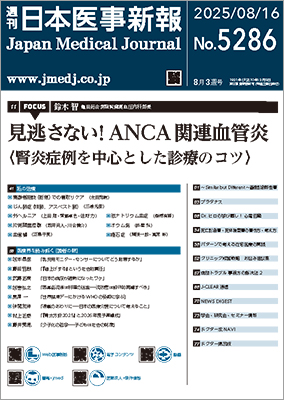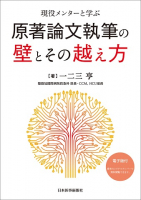お知らせ
学会レポート─2025年米国糖尿病学会(ADA)[J-CLEAR通信(180)]

米国糖尿病学会(ADA)の第85回学術集会が6月20日から4日間、米国シカゴで開催された。肥満大国米国の学会ということもあり、抗肥満薬の見本市と見紛うばかりのプログラムだった。
ここでは新たな機序を有する抗肥満薬による体組成への影響、ならびに既存血糖降下薬の臓器保護を取り上げる。

TOPIC 1
肥満例におけるセマグルチド除脂肪体重減少をビマグルマブが抑制:RCT“BELIEVE”
GLP-1受容体作動薬(GLP-1RA)による減量作用は、多くのランダム化比較試験(RCT)で実証されている。しかしそれらの薬剤で懸念されているのが、体組成への悪影響である。すなわち脂肪が減少するにとどまらず、筋肉量も必要以上に減るのではないか─。
本学会では、この点を詳細に評価するとともに、GLP-1RAによる筋肉減少を抑制しうる薬剤の存在が明らかになった。アクチビンⅡ型受容体拮抗作用を持つモノクローナル抗体、「ビマグルマブ」である。RCT“BELIEVE”の結果、明らかになった。報告には、メインの結果を担当したルイジアナ州立大学(米国)のSteven Heymsfield氏ら、4人が登壇した。
【対象】
BELIEVE試験の対象は「BMI≧30」(肥満関連合併症があれば「BMI≧27」)の507例。米国と豪州、ニュージーランドで登録された。平均年齢は47.5歳。平均体重は107.5kg、BMI平均は37.3だった。体組成を見ると、総脂肪量が45.8kg、除脂肪体重は58.3kgだった。なお、アジア人は3.0%のみである。
【方法】
これらは以下の4群にランダム化され、48週間観察された。すなわち、「ビマグルマブ単剤」、「GLP-1RA(セマグルチド)単剤」、「ビマグルマブ・セマグルチド併用」、プラセボ─の4群である。
ビマグルマブ群、セマグルチド群とも低用量群と高用量群が設けられていたが、紙幅の関係でセマグルチド群は高用量である2.4mg/週皮下注(57例)、同じくビマグルマブ群も高用量30mg/kg(1、4、16、28、40週に静注。57例)、同様に両剤併用群も高用量併用(57例)のデータのみを示す。
【結果】
・体重の変化(1次評価項目)
試験開始48週間後の減量幅は、プラセボ群が2.5kg、ビマグルマブ群10.7kg、セマグルチド群15.5kg、ビマグルマブ・セマグルチド「併用」群21.9kgだった。
・脂肪量の変化
脂肪量はDXAで評価した1)。ビマグルマブ群における脂肪量の試験開始からの低下率は25.3%で、セマグルチド群の24.8%と同等だった。また、これら両剤併用群では42.4%という低下率を観察した(いずれも開始前に比べ有意低下)。一方、プラセボ群における低下率は5.2%で、有意差に至らなかった。
内臓脂肪量の目安である「腹囲径」でも、同様の変化が認められた。ここまでは、ビマグルマブとセマグルチド間に大きな差はない。
・除脂肪体重
一方「除脂肪体重」では、ビマグルマブとセマグルチドの差が際立った(体重から骨重量と脂肪重量[いずれもDXA評価]を除した値)。
まずセマグルチド群だが、除脂肪体重の低下率は7.9%だった(vs. 試験開始時。プラセボ群に比べ有意に大)。ところが同剤にビマグルマブを併用すると、低下率は2.6%のみに抑制されていた(セマグルチド群と有意差、プラセボ群とは有意差なし)。
さらにビマグルマブ群では、試験開始時から2.3%の有意な除脂肪体重「増加」が認められた。なおビマグルマブには既に、健常高齢者における筋肉量増加が報告されている2)。
続いて、「体重減少に占める除脂肪体重減少の割合」を算出した。するとセマグルチド群では28.5%に上った一方、ビマグルマブ群では0%、両剤併用群も7.1%のみだった(群間の検定は示されず)。
・カロリー摂取量
もう1点目を引いたのが、ビマグルマブのカロリー摂取に対する影響である。ビマグルマブ群では先述の通り、脂肪量はプラセボに比べ有意に減少していた。にもかかわらず試験開始24週間後のカロリー摂取量減少幅は、プラセボ群よりも小さい傾向を認めた。
・安全性
いずれの群も重篤な有害事象、予想外の有害事象は認めなかった。
ただしビマグルマブ群では1点、懸念されるデータもあった。LDLコレステロール(LDL-C)である。というのも、ビマグルマブ群では開始24週間後まで、30%近いLDL-Cの急峻な上昇を認めた。その後は緩徐に低下し続けたが、開始48週間後でも開始前に比べ25%近い有意高値となっていた(その後も低下は継続)。
一方、セマグルチドを併用すると、ピーク時のLDL-C値はビマグルマブ群と同等ながら、その後の低下はより急峻だった(セマグルチド単剤ではLDL-C軽度低下)。
この部分を報告したワイル・コーネル医科大学(米国)のLouis Aronne氏は、既にジェネリックのストロングスタチンが使える以上、この程度のLDL-C上昇は大きな問題ではないとの見解を示した。
◆
過去数年、インクレチン関連薬が話題の中心となってきた減量治療だが、新たなプレーヤー登場となるだろうか。日本人での検討が待たれる。
本試験のsponsorはEli Lilly and Company、Collabo-ratorはVersanis Bio, Inc.である。学会報告では試験に対する資金提供の開示はなかった。
TOPIC 2
GIP/GLP-1RAとGLP-1RAによる2型DM例CV転帰改善作用を比較:SURPASS-CVOT試験エミュレーション
GIP/GLP-1受容体作動薬(GIP/GLP-1RA)であるチルゼパチドは、2型糖尿病(DM)例の心血管系(CV)イベントを抑制するだろうか─。
意外なことに、この点を1次評価項目に据えた大規模ランダム化比較試験はまだ報告されていない。現在、2型DM 1万3299例をチルゼパチド群とGLP-1RAであるデュラグルチド群にランダム化したSURPASS-CVOT試験3)で検討中である(臨床試験登録サイト“ClinicalTrials.gov”4)では2025年6月終了の予定だが、いまだに終了の発表は聞かれない[7月15日時点])。
そこで本学会では一足先に、実臨床データを用いてSURPASS-CVOT試験をエミュレーション(模倣)した比較5)が、ブリガム・アンド・ウィミンズ病院(米国)のJohn W. Ostrominski氏により報告された。
実臨床におけるCV転帰改善に、両剤間で大きな差はないのかもしれない(SURPASS-CVOT試験の主たる目的は、チルゼパチドの「非劣性」証明)。
【対象】
今回の解析対象は、SURPASS-CVOT試験と同じである。すなわち、アテローム動脈硬化性心血管疾患(ASCVD)既往を有する「BMI≧25kg/m2」の2型DM例で、主たる除外基準は「重度の心不全や腎機能低下」などである。
これらに該当するチルゼパチド開始2万2715例とデュラグルチド開始1万1764例を、米国の民間保険会社データベースから抽出し、傾向スコアを用いて125項目の背景因子をマッチできた各群9233例を比較した。
平均年齢は69歳、女性が51%を占めた。なおSUR PASS-CVOT試験における平均年齢は64.1歳、女性の割合は28.9%のみである。さらにHbA1c平均値も、本解析が7.6%だったのに対し、SURPASS-CVOT試験では8.4%という高値だった。一方、高血圧合併率はいずれもおよそ90%、脂質異常症も85%強で、本解析とSUR PASS-CVOT試験間に大きな差は認めなかった。
【結果】
その結果、チルゼパチド群では、本解析における1次評価項目である「総死亡・心筋梗塞・脳卒中」ハザード比が、デュラグルチド群に比べ、0.80(95%CI:0.65-0.99)の有意低値となった。ただし治療必要数(NNT)は「124/年」である(追跡期間は最長1年間。中央値は5.0カ月)。
両群のカプランマイヤー曲線は3カ月後から乖離を始め、9カ月過ぎまで差は開き続けたが、それ以降はほぼ平行だった(12カ月時点での例数はチルゼパチド群:1849例、デュラグルチド群:1078例)。
1次評価項目の内訳を見ると、チルゼパチド群で著明に低下していたのは「総死亡」のみで、「心筋梗塞」と「脳卒中」リスクは両群でほぼ同等だった。ちなみにOstrominski氏によれば、チルゼパチド群ではデュラグルチド群に比べ、肺炎や敗血症などの重症感染症の発生率が、有意差には至らぬものの低かったという。
なおSURPASS-CVOT試験における1次評価項目は、本解析と異なり「CV死亡・心筋梗塞・脳卒中」である。今回の解析では「CV死亡」データが入手困難だったため「総死亡」に置き換えたという。
SURPASS-CVOT試験の結果が待たれる。
本研究に対する資金提供については、開示がなかった。
TOPIC 3
安定CAD合併2型DM例へのSGLT2阻害薬EAT減少作用は4年間持続:小規模RCT 4年延長観察
SGLT2阻害薬は、安定冠動脈疾患(CAD)合併2型糖尿病(DM)において、4週間服用で心外膜脂肪(EAT)の「厚み」と「糖取り込み」を減少させる。この結果は2023年、14例と対象数は少ないものの、ランダム化比較試験(RCT)である“DAPA-HEART”6)で報告されている。とはいえ、この作用は長期間維持されるのか─。
この問いに答えるべく同試験を4年間延長した観察結果が、本学会で発表された。報告者は、サクロ・クオーレ・カトリック大学ローマ校(イタリア)のCassandra Morciano氏。
SGLT2阻害薬による心臓への作用は、長期間にわたり持続するようだ。
【対象】
DAPA-HEART試験の対象は、安定CADを合併した40歳以上の2型DMの14例である。主な除外基準は、「心筋梗塞既往」や「NYHAⅢ度以上心不全」、「左室駆出率≦50%」、「中等度以上腎機能低下」だった。
試験開始時のHbA1c平均値は7.9%。体重平均は81.1 kg、BMI平均は28.5kg/m2である。
【4週間観察】
これら14例はSGLT2阻害薬群(ダパグリフロジン10mg/日)とプラセボ群にランダム化され、二重盲検下で4週間観察された。
その結果、SGLT2阻害薬群ではプラセボ群に比べ、EATの厚みが相対的に19%有意低下し、同時にEATによる糖取り込みも相対的に21.6%抑制した。改善されたのはEATだけではない。冠血流予備能(CFR)も、SGLT2阻害薬群でのみ相対的に35%の有意(P=0.008)増加を観察した(論文未収載)。
【4年間観察】
今回の報告のメインは、これらの4年間延長観察である。上記4週間観察後、全例がSGLT2阻害薬(ダパグリフロジン10mg/日)を服用の上、盲検化されることなく、さらに4年間観察された。ただし4年間観察を継続できたのは、14例中9例のみである。
まずEATだが、SGLT2阻害薬による減少作用は、4年後まで維持されていた。すなわち、上記4週間観察SGLT2阻害薬群におけるEATは4年後、有意差には至らないものの、さらなる低下傾向が認められた。また当初のプラセボ群でも、4週間観察終了時のSGLT2阻害薬開始に伴い、4年間観察後のEATは有意に減少した。両群を合わせると、4年間観察後におけるEATは相対的に29%の有意低値となった。
なお、これら全例でBMIとの相関を検討したところ、BMIの減少幅とEAT減少幅の間に有意な相関は認められなかった。SGLT2阻害薬によるEAT選択的な減少作用が示唆される。SGLT2阻害薬に伴うEAT減少の機序として「白色脂肪細胞の褐色細胞化」を、Morciano氏は想定しているという。
一方、SGLT2阻害薬によるCFR増加作用も、4年間維持されていた。すなわち、試験当初のSGLT2阻害薬群では、4週間観察後と4年間観察後のCFRに有意差はなかった。また、当初のプラセボ群でも、4週間観察終了時のSGLT2阻害薬開始により、4年後のCFRは有意に増加していた。
SGLT2阻害薬使用によるCFR改善の機序として、EAT炎症の抑制をMorciano氏は挙げている。その上で、これら心臓への直接作用も、SGLT2阻害薬による2型DM例の心血管系イベント抑制に貢献しているのではないかと同氏は考察していた。
本試験は当初4週間観察時、AstraZenecaから一部、資金提供を受けた。その後4年間観察における資金提供の有無は不明である。
【文献】
1) Scherzer R, et al:Am J Clin Nutr. 2008;88(4):1088-96.
2) Rooks D, et al:J Cachexia Sarcopenia Muscle. 2020;11(6):1525-34.
3) Nicholls SJ, et al:Am Heart J. 2024;267:1-11.
4) ClinicalTrials.gov ID:NCT04255433.
5) ClinicalTrials.gov ID:NCT06779929.
6) Cinti F, et al:Cardiovasc Diabetol. 2023;22(1): 349.