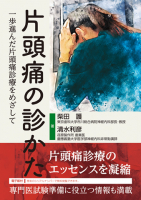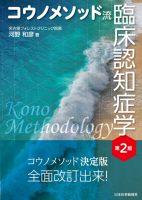お知らせ
硬膜穿刺後頭痛(腰椎穿刺後頭痛)[私の治療]

硬膜穿刺後頭痛は,腰椎穿刺後に生じる低髄液圧が原因で発現する頭痛である。臨床的には,硬膜穿刺による穿刺部位からの脳脊髄液漏出に起因する起立性頭痛が特徴である。立位もしくは坐位にて頭痛が発現し,臥位になることで速やかに消失する。悪心,首の痛み/こわばり,光過敏や耳鳴,聴力変化を伴うことがある。
頭痛発現のメカニズムは,脳脊髄液圧の低下により頭蓋内組織が下垂をきたし牽引性頭痛が生じるという説と,脳脊髄液の減少により硬膜静脈洞や架橋静脈が拡張するため痛覚受容体が刺激されて生じるという説などがある。
通常は時間経過とともに起立性頭痛の特徴は不明瞭となるので,穿刺後に発現した起立性頭痛であることを病歴で確認することが重要である。ほとんどの場合は穿刺部が自然に閉鎖するため2週間以内に軽快する。
国際頭痛分類1)の低髄液圧による頭痛の診断基準は次のとおりである。①頭痛は低髄液圧もしくは脳脊髄液漏出の発現時期に一致して発現した,②またはその頭痛が低髄液圧発見の契機となった,③かつ髄液圧が60mmH2O未満と画像検査における脊髄液漏出の根拠の両方あるいはいずれかを満たす。ただし腰椎穿刺が原因となっているので,再度穿刺して髄液圧を確認することは避けるべきである。
腰椎穿刺の際は髄液漏出を最小限にするため,穿刺針は25~27Gの細いものを使うのが望ましい。さらに穿刺後1~2時間はベッド上安静にすることが推奨される2)。
▶診断のポイント
腰椎穿刺後から5日以内に発現した頭痛であることと,その頭痛が坐位または立位をとることで誘発され,臥位をとると速やかに改善するという起立性頭痛の特徴を確認することが重要である。ただし穿刺後1週間以上経過している場合は,このような起立性頭痛の特徴が不明確になるので病歴聴取が重要である。

臨床経過より診断が可能であることから,漏出を確認するためのガドリニウム造影MRIなどの検査が必要となることは稀である。

残り832文字あります
会員登録頂くことで利用範囲が広がります。 » 会員登録する