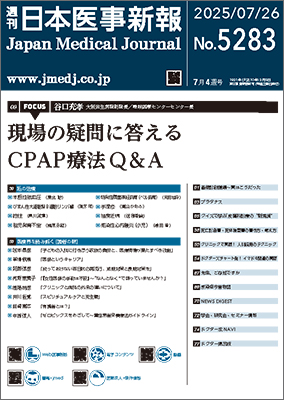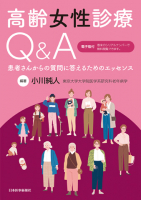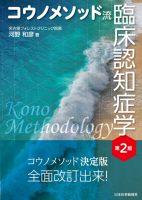お知らせ
【識者の眼】「アルツハイマー病の血液検査、臨床導入にあたっての視点」内田直樹
2025年5月、米国食品医薬品局(FDA)は、富士レビオ社製の血液バイオマーカー検査を、55歳以上の認知症が疑われる患者におけるアルツハイマー病の診断補助として承認した。これは神経変性疾患領域において画期的な動きであり、今後の臨床現場への影響も大きい。しかし、その利点と限界、そして誤用のリスクを正しく理解する必要がある。
利点:陰性結果がもたらす医療資源の最適化
最大の利点は、陰性と判断できれば、アルツハイマー型認知症ではない患者に対して抗認知症薬を漫然と処方することを避けられる、という臨床的な意義にあると考える。現状、アルツハイマー病の過剰診断とそれに伴う抗認知症薬の過剰処方が懸念されており、本検査はその是正に資する可能性がある。

加えて、陰性結果によってPET検査や脳脊髄液検査といった高額、または侵襲的な精査を回避できる意義も大きい。特に地方都市や在宅医療の現場では、PET検査へのアクセスそのものが困難な場合も多く、血液検査でリスクが低いと判断できれば、患者負担・医療費の双方を軽減できる。
認知症=アルツハイマー病という誤解
現場ではいまだに「認知症=アルツハイマー病」と考える一般市民や一部医療者も少なくない。だが実際には、認知症の背景には多様な原因疾患があり、正確な鑑別こそが治療・ケアの方向性を定める上で不可欠である。
この血液検査は、あくまで「アルツハイマー病病理の可能性を補助的に示す」ものであり、認知症の包括的診断に代わるものではない。
注意:スクリーニングには用いてはならない
FDAも明言する通り、本検査は認知機能の低下が明らかになった後に「診断補助」として用いるべきであり、「将来のアルツハイマー病の発症リスクを調べる」といった目的でのスクリーニングには不適切である。
これは、米国の有名なNun Studyでも示されている通り、アルツハイマー病の病理変化(アミロイドβ沈着やタウ蛋白の蓄積)と認知症症状の発現とは必ずしも一致しないためである。生前にまったく認知機能の低下がみられなかったにもかかわらず、死後の脳で高度なアルツハイマー病理が認められた症例も報告されている。
こうした乖離がある以上、「リスク判定」や「予防」の名目で無症候の人に本検査を提供することは、医学的にも倫理的にも不適切である。誤って陽性と判定された場合、必要以上の不安、保険・雇用上の不利益、さらには不適切な介入へとつながるおそれがある。
まとめ
今回の血液バイオマーカー検査は、今後の認知症診療における選択肢を広げる重要な一歩である。しかし、その導入にあたっては、対象となる患者像(認知機能低下が明らかな患者)を厳密に限定し、診断補助として位置づける必要がある。
本検査を「安価で簡便な認知症リスク検査」として自由診療などで広めていくことは、誤診と不安の拡大をまねき、かえって医療の質を低下させかねない。医療者には、科学的根拠に基づいた丁寧な説明が求められる。
内田直樹(医療法人すずらん会たろうクリニック院長)[アルツハイマー病][血液検査]