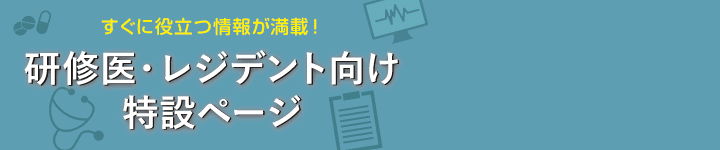お知らせ
広島時代の日野原重明先生[エッセイ]
都心を離れた閑静な住宅街にある日野原重明先生のお宅を訪ねたのは、先生がお亡くなりになる4カ月前の3月3日のこと。ラジオNIKKEIからの依頼で、広島時代の話をお伺いするためだった。2年ぶりにお会いした先生は、その時よりも明らかに弱っていらした。それでも記憶を辿るという風ではなく、80年以上前の話をつい昨日のことのように語ってくださった。
神戸育ちの先生が、結核を発病して広島で2年間の療養生活を送られたのにはわけがある。先生が三高、京大と京都で学生生活を送っていた間に、父君の善輔先生が広島女学院長に招聘され、ご一家は神戸から広島へと居を移されていたのである。

発病当時(1933年)、結核は死の病として人々に恐れられていた。先生も自叙伝『僕は頑固な子どもだった』(2016年、ハルメク刊)の中で、「当時、結核は不治の病とも言われており、先の見えない不安に苛なまれる」と記していらっしゃる。当然、先生も結核を患ったこの時期、死を意識されたはずである。その後の先生の人生、特に医師としての死生観に大きな影響を与えたに違いない。取材前、私は単純にそのように考えていた。
ところが、そのことを伺うと、先生は「確かにショックを受けたが、死をまともに意識することはなかった。学校を休んだ時も休学届を出さなかったのだよ」と軽く受け流された。予期せぬ答えであったが、先生へのさらなる理解を深めるきっかけになったような気がする。
日野原先生が死を意識し、医師としての自分の生き方を大きく変えたきっかけは、「よど号ハイジャック事件」だったと自叙伝(前出)にある。4日間の人質生活から解放され、羽田空港の地を踏んだ時の、足で感じた土の感覚が今も残っている、と。
この事件を通して先生が医師としての更なる歩みを始められたことは、その後の先生のご活躍をみればよくわかる。自叙伝でも、「許された第二の人生が多少なりとも自分以外のことのために捧げられればと希ってやみません」と記されている。先生は当時58歳。普通の人間ならば、定年間近の年である。しかし、105の春秋を経験した先生にとっては、人生のちょうど折り返し点に過ぎなかったということだ。
「先生、まだやることがあるのですか?」という私の不躾な問いに、「来月はじめ、看護大生の入学式があるので、そこに出席しなければならない。いま体調を整えているところだよ」と笑顔で返された。ところが、私のインタビューの数日後、先生は肺炎のために聖路加国際病院へ一時入院され、7月18日未明、ご自宅から神様の御許へと召された。
訃報を伝えてくださった秘書の佐藤玖子さんに、私は気になっていた入学式のことを伺った。先生は入学式に出席こそできなかったが、ビデオレターで「エイエイオー」と新入学生にエールを送ったとのこと。カメラに向かって顔をあげ、こぶしを突き上げる先生の姿が目に浮かぶようで、思わず「さすが日野原先生」と言って、佐藤さんと二人で笑ってしまった。105歳までの長寿の秘訣ではなく、老いをいかに豊かに生きるか。それが、先生からいただいた最後の教えだったような気がする。
重明先生にとって短い広島時代のことを伺ったのであるが、いま振り返れば実に楽しい取材であった。先生が「番組の中で流してほしい」と選ばれた愛唱歌は、「ちいさなかごに」だった。米国で作詞・作曲された讃美歌であるが、先生が幼稚園時代(100年前!)に覚えたというその歌を一緒に歌わせていただき、久しぶりにオルガンの伴奏までできた。また、80年前の私の父や母、さらに原爆で死亡した祖母の様子まで先生から伺うことができた。

残り765文字あります
会員登録頂くことで利用範囲が広がります。 » 会員登録する