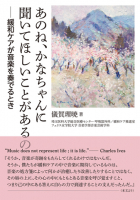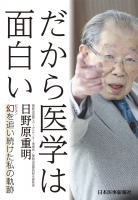お知らせ
ヘッセの『やすらぎの家─サナトリウムに住むある男の手記』[エッセイ]
1909年にヘルマン・ヘッセ(1877〜1962)が発表した『やすらぎの家─サナトリウムに住むある男の手記』1)には、ある種の理想的な療養所とそこに勤める医師の姿が描かれている。
この作品は、「1年ほど前から私が住んでいる『やすらぎの家』は、『保養施設』という控え目な、感じのよい名前がついており、なにかホテルとサナトリウムの中間のようなものである」という一文で始まる。この施設の入所者は、「本当のホテルで生活するほどの元気も抵抗力ももうないが、そうかと言って本当のサナトリウムに入る決心をするほどの勇気もないか、またはそこまで絶望してはいないといった人たち」だったのである。
この施設は経験豊かな婦人らによって営まれていて、入所者に対して「かかわりを持つことは控えられ、監視は気づかぬように廊下でそっとなされるという上品な装いの中で、客としての尊敬が受けられる」というような対応がなされていた。
この施設が受け入れる客はせいぜい20人で、もっぱら自室で生活している重症の5、6人の病人を除けば、「ほとんどみながお互いに紹介しあい、いくらか控えめで和やかなつきあい方をしており、じゃましあったり、犠牲を要求しあったりすることはない」。
この施設では「病弱であり、養生し元気をつける必要があるあらゆる種類の人たち」が生活しているのであって、「彼らはここで、落ち着き、森の空気、湯治場、気持のよい世話、便利な散歩道、穏やかな気候などを得るとともに、よく考えてつくられた、慣れることの容易なよい食事を得ることができる」。その特徴は「日常と正常な生活から、つまり仕事や職業から、また就業生活の興奮や苦労から、一時的または長期的に遠ざかること」で、ここでは各自の仕事について話されることもなかった。
こうした気風は主治医である教授の気風によるもので、教授が治療するのは「病気ではなく人間」だった。教授にとって重要なのは「病人たちに生きることを楽にしてやり、彼らの制限された、または害された体質という条件の中で、できる限り好ましく我慢のできる生き方を提供したり、身につけさせたりすること」であって、そんな彼の態度は「不治の病にかかった人を恐れて尻込みせず、重篤な人を見放さず、危篤の人の数分間も、軽い病人の数年間に劣らず耐えられるものにし、可能な限り快適なものにしようとする」ものだった。
教授は、病気と健康の中間に位置するフレイルのような状態へのケアにいち早く取り組むとともに、治療困難な人でも見捨てずに最後までケアするといった対応をするなど、患者の心身のやすらぎやQOL主体の医療を心がける医者だったのである。
また教授は、「人が生れもっている体質をむりやり変えようとせず、虚弱な人を丈夫にしたり、やせた人を太らせたりしようとせず、だれにでも、たとえひどい病気のままだとしても、その境遇や体質を持ちこたえることを可能にし、容易にしようとする」といった対応をしていたともされているから、患者のあるがままを尊重し、心身両面でその人らしく生きられるように心がけていたという点でも、時代に先駆ける現代的な医師だったという。
こうした教授の基本にある考え方は、「生きている自然のあらゆる現象を先入観なしに気高く敬うこと、人間のすべての状態、つまりあらゆる境遇と激情と錯誤をほとんど道義にとらわれることなく判断する」というものだったとされているから、教授はすべての人間の価値を平等に尊重するという考え方をしていた人のようにも見える。
もっとも、そうした教授の治療の限界を感じさせる患者もいた。それはまだ40歳にもならない有名な作家で、入所して最初のうちは周囲に打ち解けず、孤独で傲慢に見えた。そのため彼は、「本来は傷つきやすく、内心では控え目なのに、思いあがった粗野な人間」と思われていたのだが、実は彼は「己の欠点から身を守る術を、無愛想で不機嫌な態度以外に知らなかった」だけだったのである。
この作家の病については、「自らの悪い状態や不眠、そして様々な肉体的苦痛の元にはからだの病気があるのだというこの作家の思いこみ、この思いこみは1つの狂気だが、それは医者によって発見され、破壊された」とされているから、彼は自分が重篤な病気に罹っていると思い込む心気症のような状態にあったと思われるが、それが教授の治療によって一定程度改善したとされているのである。
しかし、その一方でこの作家は自らの創作活動について、教授の治療を受ける過程で、「自制のきかない精神の暗い衝動とともに、芸術家としての創造的な力も失われてしまう」と感じていたのではないか、と主人公は推測している。この作家は、この施設での治療が進展するにしたがって、「己の思考と精神の構造に終止符を打ち、それによって、抑制されてしまってはいるが、より安定した苦しみのない生の喜びを獲得する」のか、それとも「デーモンに暗闇を思うまま支配させ、ごくまれに訪れる陶酔的な高められた時のために、落ち着きというあの安定した幸せを断念する」のかという二者択一に迫られたのではないか、と主人公は推測するのである。
つまり、心身のやすらぎをもたらす教授の治療は、精神的な安定をもたらすというそのこと自体によって創造的な活動にはマイナスに働くと作家が考えたのではないか、と主人公は推測しているのである。そこには、精神的な安定は必ずしも創造的な活動に寄与しないという病跡学的な発想を見ることもできる。そして、そのような見方からすれば、教授の治療に病跡学的な疑念を抱いた作家というのは、実は1927年に発表した『荒野の狼』2)でも「苦悩の天才」というような病跡学的な考えを述べているヘッセ自身ではなかったかと思われる。実際、半ば理想化して描いている教授の治療についても、「病気の者、道に迷った者、本当の生活ができなくなった者にとっての一種のモルヒネ、すなわち気休めでしかないのだろうか?」と疑問を投げかける一文で、この作品は終わっている。
【文献】
1)ヘルマン・ヘッセ, 竹岡健一, 訳:やすらぎの家─サナトリウムに住むある男の手記. ヘルマン・ヘッセ全集 第6巻. 臨川書店, 2006.
2)高橋正雄:総合リハ. 2005;33(9):884.