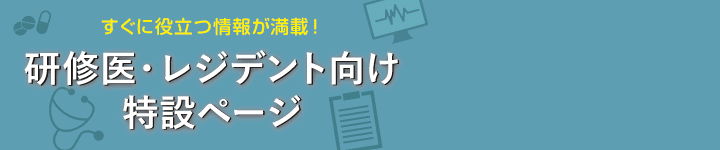お知らせ
島木健作の『醫者』─続・文学にみる医師像[エッセイ]
島木健作が1934(昭和9)年に発表した『醫者』(『島木健作全集第1巻』、国書刊行会刊)には、戦前の刑務所に勤める山田という医師が描かれている。山田は大学を出るとすぐ外科の研究室に入って学位論文を仕上げるつもりだったが、少しでも早く指導教授に学位論文の研究題目を指定してもらおうとする研究生同士の暗闘や賄賂沙汰を目のあたりにして、1年余りで研究室を去ったのである。
山田が監獄医を選んだのは、そこに何か浪漫的なものを感じたからだが、彼が赴任した日、典獄は彼に、「収容者は決して憎むべき犯罪者として取り扱ってはならない、彼らはみんないろいろな意味で気の毒な病人である、刑務所の職員は全員協力してこの病人の病気を治し、これを健全な人間にしてその委託によって一定の年限あずかっていた社会へ送り返さねばならない」と説いた。
こうした典獄の人道的な言葉に、山田は共感と興奮を感じた。また、刑務所内の病舎も「異国の地にあるサナトリアム」を思わせる立派な建物で、見学者を案内する役人は、「ここは病舎です。社会の一流病院にも劣らないだけの万般の設備がととのっています。レントゲンまでそなえてあります」、「当所も昨今はいよいよ衛生方面に留意いたしまして、その結果、収容者の罹患数もほとんど半減するにいたりました」と、紹介するのが常であった。
若き山田医師の願いは、この建物の内部も、その外見と一致したものにすることだった。「瘠せぎすの背の高い」彼は、毎朝10時になると廊下に姿を現し、部屋の扉を開けて一人一人の寝台の側に近づいては、「どうかね、変りはないかね」、「どこか苦しいかいってごらん」、「御飯はよく食べられるかね」などと聞いて回った。そして、苦痛を訴える患者があれば、寝台の端に腰を下ろして熱心に患者の話を聞いたが、それは、窓の外から部屋の中を覗き込み、「どうだ、変りはないか?」とだけ声をかけて、患者が何かを訴えようと窓のほうへ近づいてくるときには4、5間も先の廊下を歩いているといった、前任者の態度とは異なるものだった。
もっとも、収容者たちは、こうした山田の態度をいぶかしみ、彼が優しくすればするほど警戒したが、ある日山田は、広く美しい庭に出て運動している囚人たちの姿を見て、担当看守に尋ねた。「病人の運動時間は何分でしたかね」、「15分です」、「そうですか―明日から一つ30分にしてやって下さいませんか」。
ある日、山田が宿直の夜に電話が鳴った。宿直といっても普段は夜中に一度病舎を回るだけで、あとは自宅で待機していればよかったのだが、この日は雑居房からの呼び出しである。行ってみると、薄暗いあかりの下に不安におびえる10人ほどの顔が並び、その中央には、若い男が腹を押さえて悶え苦しんでいた。額には玉の汗が流れ、荒々しい息の音がしーんとした房の中に聞こえる。


残り1,452文字あります
会員登録頂くことで利用範囲が広がります。 » 会員登録する