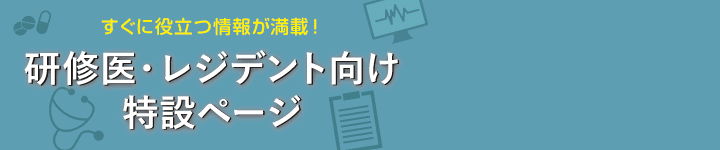お知らせ
精神医学的漱石論(1)─作家・評論家による病跡学 [エッセイ]
筆者はこれまで本欄で、国文学者が精神医学的観点から花山院や紫式部を論じた病跡学的論考を紹介してきたが、もう1人、多くの作家や評論家が精神医学的な見解を述べている人物がいる。夏目漱石である。漱石については、精神科医のみならず、少なからぬ著名な文学者が、その病理を論じているのである。
そこで、本論では、昭和40年代に発表された大江健三郎、中村真一郎、大岡昇平という3人の作家・評論家によって執筆された漱石論に着目して、その病跡学的な見解を検討する。
大江健三郎の『作家は文学によってなにを もたらしうるか?』
1966(昭和41)年に発表された『作家は文学によってなにをもたらしうるか?』(『大江健三郎全作品4』、新潮社刊)には、漱石に関する大江健三郎の病跡学的な見解が示されている。
大江は、漱石が1914(大正3)年に書いた『日記及断片』を「孤独な激しく鬱屈する人間」の「全体的な自己表現の響きが、われわれの胸につたわって来ずにはいない文章」と評価する姿勢を示して、その中の次のような文章に注目している。「私が下女に何々して下さいと言うや否や安倍はいきなり同じ様に歯を鳴らし出した。そうしてそれを何遍もやるから君は歯が痛いかと聞いた」、「私の方でも歯を鳴らした。すると安倍の方でも已めない、いつ迄も不愉快な音を出すから私はやむをえずその音はやめろと忠告した。安倍ははい已めますと答えた。しかしもう一返やっていやこれは失礼といってやめた」。
これらの文章は、当時の漱石に被害関係妄想があったことを示唆するものだが、大江もこの文章の異常性については、「作家は一個の狂人である資格を有する」、「漱石の、すでにその狂気の疑いにかかわるもの」など、その病理性を十分に認識している。
しかし、その一方で大江は、「人はなぜこのような文章を書くのか?人はこのような不安のうちにあって、なぜ沈黙しつづけていることができないのか?」と、そもそも漱石は、なぜ、このような病的な状態を文章にしたのかという、病と創造の関係に対する根源的な問いを投げかけながら、この病的な文章が孕む魅力を次のように語っている。「その文章は現在もなお、僕にとって深く本質的な喚起力をもちつづけている」、「書き手はかれ自身の暗い淵を覗きこみ、かれをとらえた黒い怪物を相手に苦しい闘いをいどむ状態にある」、「そのような格闘のさなかに発した叫び声とでもいうものが、われわれにつたわってきて、そこに感銘が生じるのである」。
大江は、『日記及断片』に書かれた「漱石の暗く鬱屈した苛立ちを、狂気と呼ぶことは決してあまりにまとはずれではない」と、漱石の病理性を認める一方で、「かれの緊張は、孤独なものではあるが、もっとも激しいもの」であり、その「独自の緊張によって、われわれ独自の緊張をみちびき、その緊張は、われわれをわれわれ自身の存在の根にむすびつける」として、漱石がその病的な状態の中で感じた緊張は、我々も共有しうるものであるとの認識を表明しているのである。
すなわち、大江は、漱石の『日記及断片』の中に明確に病的なものを認めつつも、そうした病的な状態の中で漱石が感じていた緊張は紛れもない真正の感情で、我々にも共感しうる感情であるとする考えを述べている。大江は、漱石が病的な状態で書いた文章に病的なものばかりを見るのではなく、「われわれおのおのの狂気にむかわしめる緊張」や「全体的な自己表現の響き」を感じて評価し、「人間としての存在の根」に関わるものを見出すという、すぐれて病跡学的な態度を示しているのである。


残り2,462文字あります
会員登録頂くことで利用範囲が広がります。 » 会員登録する