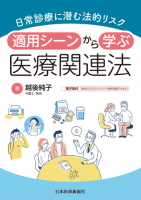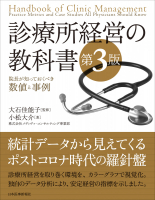お知らせ
【識者の眼】「医師の宿直体制の見直し」小野 剛
内閣府の規制改革推進会議の答申が閣議決定された。その内容を見ると、医療に関連する項目として、1.地域におけるオンライン診療の更なる普及及び円滑化、2.地域の病院機能の維持に資する医師の宿直体制の見直し、3.在宅医療における円滑な薬物治療の提供、4.一般用検査薬への転用の促進、の4項目が提示されている。
地方の医師少数区域で中小規模病院を運営する病院長の立場からすると、「医師の宿直体制の見直し」は興味深い項目であり注目している。『規制改革推進に関する答申(案)(概要)』には、「地域の実情に応じて必要な病院機能を維持するため、①宿直の例外規定にオンラインによる対応が含まれる旨明確化、②複数病院の宿直を遠隔かつ兼務可能とすることを検討」と記載され、2025年中の検討と措置を求めている。

勤務する医師数が少なく、医師の高齢化が進む中で、宿直体制を組むことが困難な中小規模病院では、宿日直許可を取得した上で、大学病院などからの宿直医の派遣によって運営しているところが多いのではないかと思われる。実際、当院でもそのような形で宿直体制をギリギリ維持している。
宿直医師兼務の提案は、宿直医師の確保が困難で、夜間の患者数が少なく、また、そのほとんどが軽症患者である中小規模病院にとっては歓迎される一案であり、地域の病院機能維持という観点から考えれば、検討に値するものと思われる。しかしながら、この提案の実現に向けて解決すべき課題も多いのではないかと考えている。筆者自身も月3〜4回程度の宿日直業務を行っているが、宿日直許可を取得しているとはいえ夜間に来院する患者がまったくいないわけではなく、時には救急搬送もある。さらに、医師数が少ないため、当然ながら全科当直であり、入院患者の急変への対応が必要である。
現場感覚からの率直な疑問として、「『複数病院』の距離が遠い場合に対応は可能か?」「急変時にオンライン対応が可能か?」「同時に患者が急変したときの対応はどうするのか?」「宿日直許可を取得しているとはいえ、宿直を兼務することはそれなりに業務量が増えることになるが、その場合『宿日直許可』の維持は大丈夫か?」「患者が最期を迎えたときにオンライン対応で患者家族は了解してくれるのか?」「万が一訴えられたときに誰が責任を取るのか?」「制度的、法的にこの仕組みは大丈夫か?」などが考えられる。今後、いろいろと議論されることになると思われるが、これらの課題や疑問の解決に結びつく議論を行って頂きたい。
患者や地域住民の不利益にならないことが肝要であり、この事業を展開しようとする地域では「新たな地域医療構想」の協議テーマのひとつとして、地域全体で議論し合意形成に結びつけていくべきと考えている。また、高齢者救急が増加する中で、「救急安心センター事業(#7119)」の全国的な整備と活用も、併せて議論することが有用ではないかと考えている。
小野 剛(市立大森病院院長、一般社団法人日本地域医療学会理事長)[宿直兼務][規制改革]