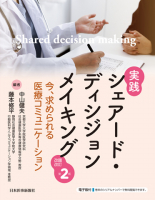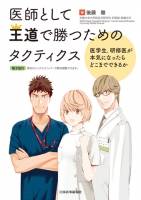お知らせ
【識者の眼】「医学教育とデリケートな部位における同意をめぐって」榎木英介
2025年5月下旬、SNS上で医学教育における「同意」のあり方、とりわけデリケートな診察における事前同意の有無が大きな議論となった。発端は、意識下あるいは麻酔中の患者に対して、医学生が内診や腟洗浄の見学・実習を行ったとの体験談が相ついで共有されたことだ。患者本人の同意が確認されていなかった例もあり、「教育のため」という名目が患者の尊厳や自律性をないがしろにしているのではないかとの懸念が表明された。
しかし、SNS上にみられたこれらの懸念に対する医師や医学生の投稿の中には、患者の感情に無理解なものや、「教育のためには当然」とする傲慢な発言があった。SNSは自由な言論の場ではあるが、医療従事者には守秘義務やプロフェッショナリズムが強く求められる。にもかかわらず、「嫌なら大学病院に来るな」といった投稿が平然と行われるのは、医療従事者としての倫理観の欠如を感じざるをえない。
焦点となっていたのは、包括的な入院同意書の効力だ。一般に、大学病院等では入院時に「医学生の見学を許可する」といった文言が盛り込まれた包括同意が取得されることが多く、腟や会陰部もそこに含まれると解釈される。
しかし、こうしたデリケートな部位の診察や処置に関しては、都度の明確な口頭同意が不可欠であるという認識が、世界的には常識となりつつある。米国では2024年に連邦レベルで、教育目的であっても無許可のデリケートな診察を禁止する法律が制定された。英国やオーストラリアなどでも、事前に書面での明確な同意を義務づけている。
この問題は、「#MeTooPelvic」という医療版#MeToo運動の文脈でも語られている。患者が知らぬ間に診察を受けることへの「侵襲感」や「トラウマ体験」は、単なる不快感にとどまらず、医療不信や精神的被害につながる深刻な問題である。さらに、医学生自身も倫理的な葛藤や罪悪感にさらされ、いわゆる「倫理的侵食」を被る危険がある。
こうした国際的潮流の中で、日本の対応は遅れていると言わざるをえない。厚生労働省は「説明と同意の重要性」を強調しているものの、医学生の診療参加に関する同意の在り方、特に「包括同意」と「個別同意」の使いわけについては明確な指針が定まっていない。婦人科ティーチングアソシエイトや泌尿生殖器ティーチングアソシエイトといった、訓練された模擬患者による実習システムの導入も、日本ではほとんど普及していないのが現状である。
医学教育と患者の権利は、対立するものではない。むしろ、患者の権利を尊重する教育こそが、真に倫理的な医療人を育てる土壌となるはずだ。
一連の投稿の中には、一部真偽不明なものがあり、そこが論点となってしまった感がある。しかし、今回のSNS上の議論を単なる「炎上」として消費するのではなく、制度的課題として受け止め、ガイドライン整備や教育手法の改革につなげていく必要がある。日本の医学教育が世界水準に追いつくためにも、「同意」という概念をより深く、より実践的に見直すべきときが来ていると思う。
榎木英介(一般社団法人科学・政策と社会研究室代表理事)[医学教育]