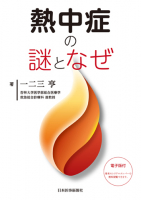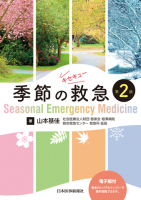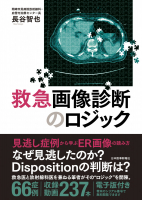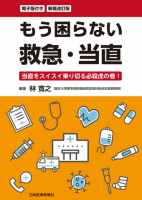お知らせ
【識者の眼】「熱中症対策の輪をひろげよう」薬師寺泰匡
熱中症での救急搬送を取り上げたニュースが増えてきている。高齢者では自宅からの搬送も多く、自宅が暑熱環境となってしまっていることを示唆している。意外と自宅から熱中症で搬送されることは多く、外出時の注意喚起はもちろんだが、自宅でしっかり休息が取れる環境を整えておくことは重要である。外出数分で搬送された事例もあるが、既に熱中症の準備が整った(ある程度症状が完成しつつあった)状態で外出して、数分で倒れてしまったものと考えられる。外出から帰宅した後に、救急搬送された事例もあった。自宅だから安全・安心というわけにはいかないのが実情である。
暑さに慣れさせる、いわゆる暑熱順化はスポーツの領域で盛んに報告されており、有酸素運動などを行う際に、何日かかけて暑熱環境に適応させることで、生理的なパフォーマンスが改善されることが示唆されている。一方で、アスリートでもない高齢者で同じことが可能になるかは不透明である。そもそも高齢者は体温調節能力が低下しており、周囲の気温変化に気づきにくい。日中の室内気温が急上昇しても、暑さを感じにくく、気が付かないうちに熱中症に至ってしまう。要するにリスクを高めるだけの行為となりかねない。エアコンや扇風機をためらわず用途に応じて活用し、日中30度を超えるような日は積極的な冷房運転が必要である。屋外に出かける際には、万全の状態を整えてほしい。

水分摂取も重要である。高齢者は渇きを感じにくく、水分摂取が追いつかないことが多い。心不全の内服治療中で、水を摂取しすぎないように指導されている場合などは、より注意が必要である。高齢者は従順に守りがちである。こまめな水分摂取が望ましいので、自宅でも時間を決め、コップ1杯の水を定期的に摂取する習慣づくりも重要ではないか。外出の際に飲み物を携行し、外出後の休憩中にも飲むことが望ましい。
行政も市町村も「室内でも熱中症になる」と警鐘を鳴らし、公共施設を「ひと涼みスポット」として開放するなど、対応に乗り出しているところもある。熱中症から命を守るには、体調管理はもちろんだが、住環境そのものへの備えが欠かせない。その意味で「自宅での準備」は、この夏に最も見直すべき生活習慣である。
我々がしなければならないことは、定期受診を中心に、「家の冷房設備」や「飲水習慣」を都度尋ね、環境を整える後押しをすることであろう。外来で、水分を持ってきているか確認したり、院内での水分摂取を促したり、熱中症予防の草の根運動を広げたい。定期受診の帰り道で救急搬送される事態は避けたいものである。
薬師寺泰匡(薬師寺慈恵病院院長)[熱中症][高齢者]