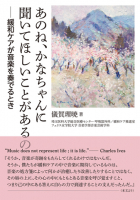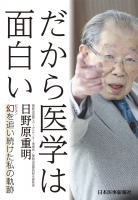お知らせ
老健施設長日記②老健施設長として50年の内科経験を現場に注ぐ[エッセイ]
老健施設けあ・ばんけい(以下、老健)では、8時30分から朝礼があり、入所者の夜間の状況について各棟から報告がある。その後、午前の回診が9時30分からあるため、介護ステーションに行くと、報告を受ける入所者のカルテが並んでいる。担当看護師より、検査結果の異常や体重の増減、熱発者の有無などの報告を受ける。
カルテには、入所となった経過が詳細に記載されている。老健の入所には、要介護1以上の認定が必要となるため、どのようなきっかけで入所に至ったのかを知っておくことは、診療をする上できわめて重要である。老健の入所者は高齢者ばかりなため、いくつもの病気を持っている方が多く、薬剤も数多く服用している。

回診ではまず、熱発者の状況を聞く。上気道炎の症状があるのか、尿が混濁していないかなど、基本的なことを尋ね、必要がある場合は診察を行う。視診と聴診が中心で、これをもとに臨床診断を考える。問診を行うにしても、認知症が進行した方では、まとまった内容を話すことができないため、会話が支離滅裂になることもある。このような場合は、看護師から助言を受けることも多い。総合的に考え、対症的な処方を行うことで、一件落着となる。
咳、痰症状の場合は、胸部X線を撮りたいが、前回もお伝えした通り、老健には設備がないため、撮影は不可能である。そのため、聴診を丁寧に行う習慣が身についた。肺炎など重篤な病気を疑った場合には、急性期病院を紹介して診察を受けてもらう。胸部X線やCTを撮り、診断がついた後、薬剤が投与される。
信じられないことに、他の病院での診療行為に対して、患者の個人負担はなく、老健が費用を負担する。介護保険の制度上、老健入所者に対する医師(管理者)の役割として、療養上のお世話と管理がある。その管理の中に、内服薬の処方や療養上の処置管理などが含まれているため、この管理にかかる費用は、「基本報酬分へ包括化」されている。つまり、高額な薬剤を必要な入所者へ提供することは、費用を老健が持ち出しているということである。
老健の経営を考える上で、よほどの重症者でなければ急性期病院の受診は避けたほうがよいということになる。急性期病院へ紹介すべきかの判断は施設長の権限であるが、この判断はきわめて難しい。急性期病院を安易に受診させると、老健の経営を圧迫することになるし、受診させる時期を誤ると入所者の生死に関わってくるからである。また、他の病院を受診するときは、家族の同行が原則として必要となるが、すぐに来てくれる方もいれば、「老健で看取ってもらうつもりなので……」と言う方もいて、家族の対応も様々である。したがって、独断で言わせて頂くと、老健の施設長は経験豊富な内科医が適任と思われる。私は内科医歴50年のすべての経験を動員して、入所者の診療に当たった。私の人生にとって学ぶことの多い貴重な1年となった。