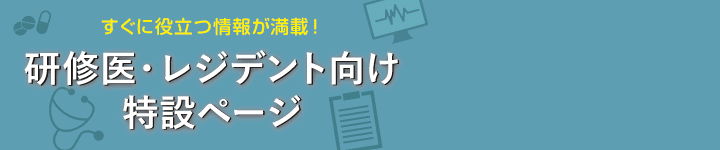お知らせ
すべては疑ってかかるべし[プラタナス]
この写真は1994年12月2日、インドネシア共和国ジョグジャカルタ市サルジット病院病棟で撮った1枚である。その後何十年も経って、この1枚の写真から多くを学んだので紹介したい。


1994年11月22日、ジョグジャカルタ近傍のメラピ火山が噴火し、噴火に伴う熱風、火砕流により多くの麓住民が熱傷を負った。この写真は救急医10年目の私が国際緊急援助隊熱傷専門家チームの一員として派遣されたときに撮ったものである。発災後1週間目、ベッドサイドのトレイには栄養補給のための大量の生卵と、何杯ものチャイが所狭しと並んでいた。私はびっくりしてシャッターを切った。なぜびっくりしたのか。日本ではありえない光景だったからである。
当時、日本の広範囲熱傷の治療の基本は、十分な輸液と高カロリーを投与するための中心静脈栄養(intravenous hyperalimentation:IVH)であった。日本ではIVH全盛の時代で、重症患者に対してはなにがなんでもIVH。そのため、受傷後1週間目の一般的な患者の様相は、輸液過多による全身浮腫、肺水腫への気管内挿管、IVHが普通であった。私は現地で専門家としてIVHの重要性を説いたが、IVHを行う医療資器材がないということで口惜しい思いをした。

残り516文字あります
会員登録頂くことで利用範囲が広がります。 » 会員登録する