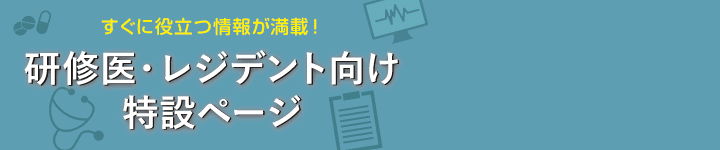お知らせ
三島由紀夫の『金閣寺』─2人の治療者[エッセイ]
1956(昭和31)年に三島由紀夫が発表した『金閣寺』(新潮社刊)には、吃音の主人公の心を慰める2人の治療者的な人物が描かれている。1人は、中学時代の友人・鶴川であり、もう1人は、主人公が金閣寺への放火を決行する日に出会う禅海和尚である。
このうち、東京近郊の裕福な寺に生まれた鶴川は、徒弟の修業を体験するため金閣寺に預けられていたのだが、鶴川は、他の級友とは違って、初めて主人公に会ったときから一度も吃音をからかおうとしなかった。幼い頃から吃音を嘲笑されたり侮蔑されることに慣れていた主人公が、その理由を問うと、鶴川は、えも言われぬ優しい微笑を浮かべて、「だって僕、そんなことはちっとも気にならない性質なんだよ」と答えた。

これを聞いた主人公は驚いた。というのも、「私という存在から吃りを差し引いて、なお私で有りうるという発見を、鶴川のやさしさが私に教えた」からである。そしてこのとき主人公は、「すっぱりと裸かにされた快さを隈なく味わった」というのだから、鶴川は、吃音という障害を抱えて鬱屈した精神状態にあった主人公に対して、治療者的な役割を果たしたことになる。
また、主人公の母親が金閣寺を訪ねてきたときにも、肉親の露骨な愛情の発露が嫌だった主人公が、「走ったかて、しょうがない。しんどいんやもん、足を引きずってかえったらええのんや」と言うと、鶴川は「そうしてお母さんに同情させて、甘ったれるつもりなんだな」と解釈しているが、そうした鶴川の行為を、主人公は次のように語っている。「鶴川はいつもこうして、私の誤解に充ちた解説者であった」、「彼は私のまことに善意な通訳者、私の言葉を現世の言葉に翻訳してくれる、かけがえのない友であった」。
主人公にとっての鶴川は、「ひとたび彼の心に濾過されると、私の混濁した暗い感情が、ひとつのこらず、透明な、光りを放つ感情に変る」ような存在だったのである。
しかし、そんな鶴川がある日突然、自殺する。しかも彼が死の直前に書いた手紙には、「今、思うと、この不幸な恋愛も、僕の不幸な心のためかとも思える。僕は生れつき暗い心を持って生れていた」と書かれていたというのだから、主人公には「透明で単純な心」の持ち主と見えた鶴川も、実は、主人公同様、暗い心の持ち主だったことになる。
しかし、そうした暗い心を抱えた鶴川が、主人公には優れた治療者としての役割を果たしていることを思うと、そこには、良き病者は良き治療者たりうるという現象を見ることができるが、主人公にはもう1人、治療者的な役割を果たす人物がいる。
それは、福井にある龍法寺の住職・禅海和尚である。禅海は、金閣寺の老師や主人公の父親と僧堂の友で、主人公の父親は生前、何かにつけて禅海のことを愉しげに話すなど、禅海に敬愛の念を抱いていた。
禅海は、たまたま主人公が金閣寺に放火する日に上洛したのだが、放火前の主人公が会った禅海は、「外見も性格もまことに男性的な、荒削りな禅僧の典型」で、「身の丈は六尺にちかく、色は黒く眉は濃かった。その声は轟くばかり」と、いかにも三島好みの男性的な人物として描かれている。
禅海については、「単純で澄明な目」、「何ものにも囚われない」といった肯定的な表現がみられるように、主人公も、「和尚には老師の持たぬ素朴さがあり、父の持たぬ力があった」と、その人間的な魅力を認めているのである。
そればかりか、主人公は禅海に人間としての優しさも感じているのであって、「轟くような大声で話す和尚には、私の心にひびくやさしさがある」、「世の常のやさしさではなくて、村のはずれの、旅人に木陰の憩いを与える大樹の荒々しい根方のようなやさしさである」、「ごく手ざわりの粗いやさしさである」と語る主人公には、「禅海和尚にだけは理解されたい」という感情が生まれるのである。
そのため、主人公と禅海の間では、次のような会話が交わされる。「私をどう思われますか」「ふむ、真面目な善い学生に見えるがのう」、「私は平凡な学生に見えましょうか」「平凡に見えるのが何よりのことじゃ」、「人の見ている私と、私の考えている私と、どちらが持続しているのでしょうか」「どちらもすぐ途絶えるのじゃ」。
こうした会話を重ねる中で、「徐々に安らぎを覚えた」主人公は、「私を見抜いて下さい」「私は、お考えのような人間ではありません。私の本心を見抜いて下さい」と訴えるのだが、それに対して禅海は、「世にも晴朗な笑い声」を立てて、「見抜く必要はない。みんなお前の面上にあらわれておる」と言うところで、この場面は終わっている。
このように見てくると、禅海和尚は、人間不信に満ちて誰にも本心を打ち明けられずにいた主人公の、唯一の理解者であり治療者でもあるような人物として、描かれている。
しかし、この半ば理想化されたような人物から、「見抜く必要はない。みんなお前の面上にあらわれておる」と言われた主人公は、その夜、かねてからの計画通り、金閣寺に放火するのだから、結果として禅海は、主人公の心を見抜くことも、癒すこともできなかったことになる。
このとき主人公は、自分の理想とするような禅海にも自分の心の奥底を見抜くことはできない、それほどまでに自分の心の闇は深いということに絶望したのであろうか? それにしては、禅海の対応に接した主人公が「私は完全に、残る隈なく理解された」と感じていることは、どう解釈したらよいのであろうか?
いずれにしても、禅海の立場に立ってみれば、主人公から「私は、お考えのような人間ではありません。私の本心を見抜いて下さい」と訴えられたときに、この若者の切迫した態度にただならぬものを看取し、安易にわかった風を装うのではなく、もう少し丁寧にその胸の内を聴いておけば、少なくともその夜、主人公が金閣寺を焼くこともなく、やがては禅海の寺で修行するという穏当な道を選択することだってできたのではないかと思えてくる。
その意味では、悟達の禅僧・禅海も、善意の翻訳者・鶴川同様、一時的に主人公の心を慰めることはできても、最終的に救うことはできなかったことになる。