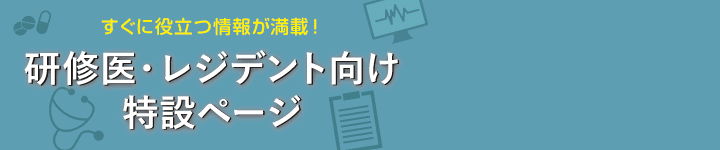お知らせ
肺癌の20年後は?[炉辺閑話]
私が呼吸器内科医をめざしたのは、最も治らない進行癌である肺癌に一石を投じたかったからである。
1985年に卒業した当時は進行肺癌の治療成績は惨憺たるもので、生存期間の中央値は10カ月にも満たない状況であった。研修医時代の非小細胞肺癌の治療はシスプラチンとビンデシンの併用療法しかなく、ほとんどの患者さんは洗面器を枕元に置いて激しい嘔気と嘔吐に悩まされた。化学療法をしなければ6カ月、やっても10カ月、その間は長期間の入院を余儀なくされ、患者さんを治療しているのか苦しめているのか悩んだ。その後、「新しい制吐剤」、「外来化学療法室」の登場で肺癌のQOLを考慮した外来治療が可能になった。しかし、肺癌治療を大きく変えたのは2002年のゲフィチニブ(イレッサ®:分子標的薬)の登場である。経口薬でありながら劇的効果がある一方、「薬剤性間質性肺炎」には落ち込んだ。その後、EGFR以外にもEML4-ALK, ROS1, BRAFなどのドライバー遺伝子変異とそれらの分子標的薬が登場し、2年を超える長期生存例も経験するようになった。その後のパラダイムシフトは「免疫チェックポイント阻害薬」であるニボルマブ(オプジーボ®)が使用可能になったことである。現在では4種類の免疫療法薬が使用可能になり、肺癌治療の一次治療、二次治療のキードラッグになっている。

分子標的薬との違いは、奏効割合は分子標的薬よりは低いものの、ある特定の患者さんを長期生存(治癒?)させる可能性がある点である。そして、更なる長期生存をめざし免疫療法と他の治療との併用療法の臨床試験が数多く行われている。また、進行・再発癌だけでなく、術前治療、術後再発予防としての免疫療法など、早期肺癌にもその適応は広がりつつある。現在の進行肺癌の生存期間は2年を超えるようになってきており、30年前と比べて約2倍になった。
さて、20年後はどうだろうか?免疫療法以外の新薬の登場、ベストな併用療法の開発、より精度の高いバイオマーカーの発見などから、間違いなく治癒する患者さんは増えるだろう。楽しみである。一方、治療薬の高騰で現在の国民皆保険下での保険制度でどこまで対応可能か不安も大きい。日本が誇るべき国民皆保険制度を守りつつ持続可能な保険制度とはいかなるものか、同時に議論が必要である。