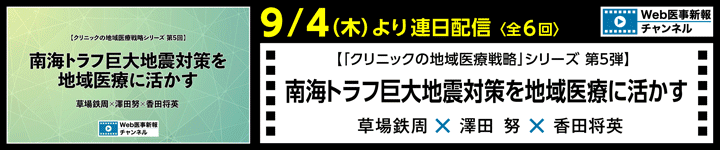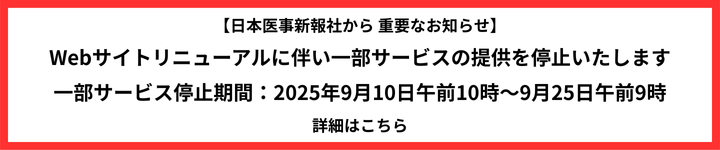お知らせ
なだいなだの『野越えやぶ越え「医車」の旅』─続・文学にみる医師像[エッセイ]
1974(昭和49)年に発表されたなだいなだの自伝的小説『野越えやぶ越え「医車」の旅』(『なだいなだ全集第4巻』、筑摩書房刊)には、なだが戦後間もない時期、フランス留学中に出会った2人の「臨床の名人」が描かれている。
❖
かねてよりフランスに憧れていたなだは、留学生試験に受かったのを契機に、インターンを中断して、一路フランスへと向かうのだが、彼が出会った名医の一人は、サルペトリエール病院で、かつてシャルコーが教授を務めていた病棟の何代目かの後継者にあたるアラジュアニン教授だった。
サルペトリエール病院には、シャルコーが講義をした講堂が残っていて、その講壇の奥には、フランス革命の最中、ピネルが精神病者の足につながれている鎖を切ったという、教科書にも載せられている有名な絵が掲げられていた。この講堂で、かつてシャルコーがヒステリー患者の臨床講義をし、フロイトがそれを聞いたのである。
また、この病棟は、さながら「珍しい病気の生きた博物館」で、日本ではほとんど見られない、教科書で名前を教えられただけの病気の患者が入院していた。その中には、何十年もベッドの上で起き上がる力もなく生き続けている筋萎縮症の患者もいたが、この患者は、「自分のためというよりは、何万人の医者に病気の末期の姿を教えるため」と、「死んだあと、脳と脊髄のアルコール漬けの標本を残すため」にだけ、生きていた。
アラジュアニン教授は白髪の物静かな老人で、失語症の臨床の大家として尊敬を集めていた。彼の診察は、「あざやかというか、もう、一つのショウというべきものであった」。アラジュアニン教授は、「弟子たちが、完全失語だと診断してしまうほど、意味のある言葉を全くしゃべれない患者を問診しながら、いくらでもしゃべらせてしまう」のである。また、彼は、「私たちにはまったく無意味な音のつらなりにしか過ぎないものの意味を、感じとってしまう」能力も持っていた。ほんのわずかな患者の発音の訛りも聞き落とさないため、なだは「名人芸というのはこういうものだろう」と思い、「臨床医学というものは、科学というよりは、一種の芸のようなものだ」と、感じている。
❖
なだがフランスで出会ったもう一人の名医が、アンドレ・トマ医師である。80歳を超えたトマ医師は、サン・タンヌ病院で1日、ヴェルレーヌが入院していたサン・ジョゼフ病院で1日、市立産院で1日、医長の許可の下、患者の診察をさせてもらっていたのである。
トマ医師は、「患者を診察するのが、そして新しい診察法を発見するのが、なによりも好き」な医者で、たとえば、患者を裸にして、腋の下から乳房の横あたりを指先でくすぐる。そして、患者の皮膚にとり肌が立つのを見せながら、「これが、とり肌反射です。自律神経反射の一つです。脊髄空洞症の患者だと、皮膚の一部分に、しまのように、あるいはすじのように、とり肌のおこらないところが出て来るのです」と説明した。
トマ医師は、「診断がついても、まるで診察そのものがおもしろくてたまらないあそびのように」、自分の知っている反射を全部調べ上げるのである。
フランスでは皆、長い夏休みをとり、教授たちは2カ月も休むのが通例である。そのため、夏の間の病院は医者が半分に減るのだが、病院の勤務医ではないトマ医師は、何一つ縛られることがないのに、夏休みに出かけようとはしなかった。彼は「まったく、医者になるために生れて来たような人」だったのである。
トマ医師が産院に通うのも、彼が「赤ん坊の友人たちとの逢引き」と呼ぶ、新生児と早産児の神経反射の研究のためだったが、彼は若い頃、学会の派閥争いから大学を離れ、個人的に研究をしていたので、専門家以外にはほとんど知られていなかった。弟子も大学関係者にはほとんどおらず、死ぬ前に4回死んだと思われたほどだが、なだがフランスにいる間、彼の赤ん坊の神経学の研究が分厚い本になって出版された。
日本に帰るなだが、トマ医師に別れの挨拶をすると、トマ医師は「君は日本の医者だろ。ヒロシマの話をしてくれないか。原爆の話を」と言い出した。大学を出たばかりのなだは、特別原爆症のことを知っているわけではなかったが、学生時代に聞いた都築博士の原爆病研究の特別講演を思い出しながら、限られた知識を総動員させて話をした。
すると、トマ医師は、話の途中で急に泣き出し、涙がとめどなく流れ出た。しかし、トマ医師は、「かまわん、かまわん。話をしてくれ。続けてくれ」、「わしは老人になった。涙もろくなった。ただそれだけだ。心配するな。続けろ」と、喚くように言った。そして、なだがヒロシマという言葉を口にすると、またひときわ声を高くして泣くのだった。「そんな爆弾を人間が作るなんてなあ、そんな爆弾をなあ、人間がなあ。わしには信じられん」。
トマ医師は、単なる診察マニアではなく、原爆の非人間性にも敏感な、優れて人間的な医師だったのである。
❖
以上が、『野越えやぶ越え「医車」の旅』に描かれている2人の医師の姿である。そこには、フランス医学の伝統たる優れた芸術家肌の臨床医が描かれているのであって、医師になる前にかかる優れた臨床家に巡り逢えたなだは、幸運と言うべきであろう。ただ一点気になるのは、サルペトリエール病院に入院していた筋萎縮症患者に関する記述である。なだは、この患者は「何万人の医者に病気の末期の姿を教えるため」とか「脳と脊髄のアルコール漬けの標本を残すため」に生きているとしているが、果たしてそうだろうか?この患者の状態の詳細はわからないにしても、ベッドに寝たきりの彼にも、彼なりの思いや感情の動きはあるはずで、病院側もそうした彼の精神状態に無関心だったとは思えない。まして教授は、名医をもって聞こえたアラジュアニン教授である。この患者は、医師のためや標本になるためだけに生きていたわけではないし、かつてピネルが勤めていた天下のサルペトリエール病院もそうした患者の心情に配慮していなかったとは考えがたいのである。