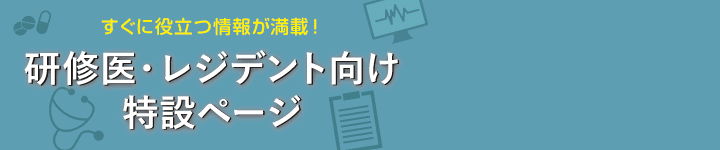お知らせ
絨毛性疾患における診断の変化
絨毛性疾患とは,胎盤を構成している絨毛(栄養膜細胞)の異常増殖による疾患で,胞状奇胎,侵入奇胎,絨毛癌などに分類される。
胞状奇胎は絨毛が嚢胞化する異常妊娠であり,わが国では1000妊娠当たり1~2の発生頻度で,その形態から全胞状奇胎(全奇胎)および部分胞状奇胎(部分奇胎)に大別される。全奇胎,部分奇胎はともに受精の異常を原因として発生し,遺伝学的には全奇胎は雄核発生,部分奇胎は3倍体であることが知られている。全奇胎は10%が侵入奇胎を,2~3%が絨毛癌を続発するが,部分奇胎からの続発症はきわめて稀である。
旧『絨毛性疾患取扱い規約(第2版)』においては,短径が2mmを超える嚢胞化絨毛を肉眼的に認めることが胞状奇胎の診断基準であった。ほぼすべての絨毛が嚢胞化しているものは全奇胎,一部の絨毛が嚢胞化している,または胎児成分を認めるものは部分奇胎と,肉眼所見で診断されていた。しかしながら,超音波断層法が普及し,より早期の奇胎診断が可能となった近年においては,典型的な肉眼所見を示さず,全奇胎と部分奇胎の鑑別が難しい症例が増加していた。
2011年7月に改訂された『絨毛性疾患取扱い規約(第3版)』では,早期の奇胎症例に対応した大幅な改訂がなされ,奇胎の診断は肉眼所見ではなく組織学的に行うことが明記された。加えて,診断が困難な場合には免疫染色,あるいは遺伝子検査を行うことが望ましいとされた。
新取扱い規約の普及により,今後は早期の奇胎症例が正確に診断されることが期待される。