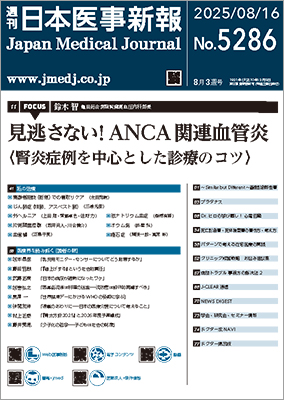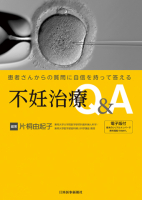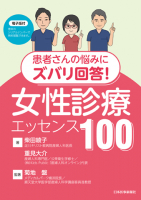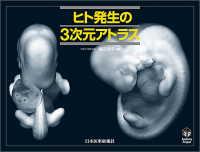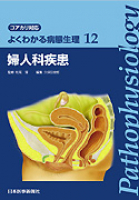お知らせ
心疾患合併妊娠[私の治療]
心疾患には,不整脈,弁疾患,成人先天性心疾患,そして周産期心筋症など様々なものがある。妊娠期は,心血管への負荷がダイナミックに変化し,増大する。心疾患の症状である動悸,息切れなどは,妊娠中〜末期の非特異的な症状でもあるので区別が難しい。
▶診断のポイント
同じ疾患でも重症度の幅は大きく,疾患名のみで対応が決まるものではない。変化する心血管を経時的に評価し,夫婦,産婦人科,循環器内科,その他多職種との十分なディスカッションが必要である。

▶私の治療方針・処方の組み立て方
丁寧な問診は欠かせず,たとえば成人先天性心疾患の場合,小児期に「根治した」と説明され,成人期にフォローがないことがある。疾患の評価は妊娠前に行われるのが理想的だが,遅くとも妊娠初期のうちに行う。ガイドライン1)に「妊娠の際に厳重な注意を要する,あるいは妊娠を避けることが強く望まれる心疾患」として挙げられる肺高血圧症や機械弁,チアノーゼ性心疾患などでは,妊娠に対する母体循環の許容範囲がきわめて狭い。
妊娠週数が進むにつれての変化も重要である。妊娠に伴い,循環血漿量が増え,脈拍数が上昇し,心血管負荷は増大する。妊婦健診は,妊娠23週末までは4週ごと,妊娠35週末までは2週ごと,それ以降は毎週であり,毎回血圧,脈拍数,体重が計測され,尿定性検査が行われる。3~4回は血液検査の機会がある。心電図,胸部X線,心エコーは,妊娠前や妊娠初期,循環血漿量が最大に達した妊娠32週以降,そして分娩後などが心機能を評価する良い機会である。大動脈疾患では,妊娠前や分娩後の造影CT,妊娠中なら単純MRIで,大動脈拡張について評価することが欠かせない。

残り1,341文字あります
会員登録頂くことで利用範囲が広がります。 » 会員登録する