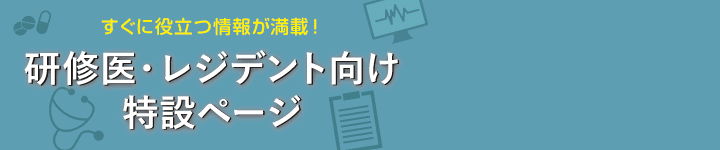お知らせ
小児・AYA世代のがん・生殖医療の課題とは?(鈴木 直 日本がん・生殖医療学会理事長)【この人に聞きたい】
「がんになっても子供が欲しい」患者の
選択肢を増やし、精神面のサポート体制も整備
地域間、施設間、診療科間の格差解消目指す
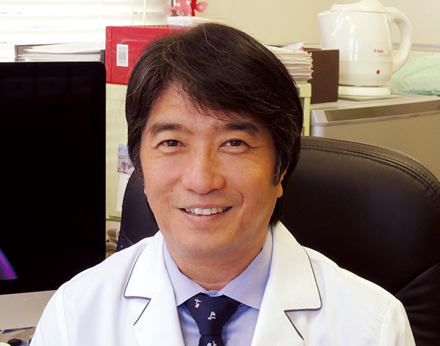
すずき なお:1990年慶大卒。2004年同大院博士課程修了。カリフォルニア州バーナム研究所留学、慶大産婦人科医長、聖マリアンナ医大准教授などを経て、11年より同大産婦人科教授。12年11月特定非営利活動法人日本がん・生殖医療研究会を発足させ、15年8月に名称を日本がん・生殖医療学会へ変更。専門は婦人科腫瘍

昨年閣議決定された国の第3期がん対策推進基本計画では、小児・AYA(思春期・若年成人:Adolescent and Young Adult)世代のがん診療の充実とライフステージに応じたがん対策が重点施策となった。2012年から小児・AYA世代への妊孕性温存療法の情報提供と支援に取り組んできた日本がん・生殖医療学会の鈴木直理事長に、その現状と課題を聞いた。
がん治療医と生殖医療医がネットワークを構築
─小児・AYA世代のがん患者が、必要に応じて、妊孕性温存療法を受けられる体制は全国に広がってきているのでしょうか。
治療を優先しつつも、小児・AYA世代は妊孕性温存療法を考慮すべきという認識は、がん治療医の間では広まりつつあります。
岐阜県では13年に、岐阜大学医学部附属病院を中心に、生殖医療医とがん治療医が連携して、妊孕性温存を望む患者さんの相談に乗り、迅速に卵子、受精卵、卵巣、精子の凍結を行うがん・生殖医療ネットワークを構築しました。岐阜県をモデルにした「がん・生殖医療ネットワーク」が、現在、約25都道府県で展開されています。
また、どこでがん治療を受けても、生殖機能を喪失する恐れがある患者さんに情報提供がなされるように、日本癌治療学会が17年に、「小児、思春期・若年がん患者の妊孕性温存に関する診療ガイドライン」を作成しました。私たちが日本がん・生殖医療研究会を発足させた12年と比べると、急速にこの問題への関心は高まりました。ただし、がん治療医と生殖医療医の連携には地域格差、施設間格差があるのが実情です。
診療科によっても温度差があり、乳腺科、婦人科、血液内科、小児科では、妊孕性温存療法について、治療前に、患者さんに情報提供するのが一般的になってきている一方、骨軟部腫瘍科、消化器科、泌尿器科などでは、この問題への認知度が低い面があります。