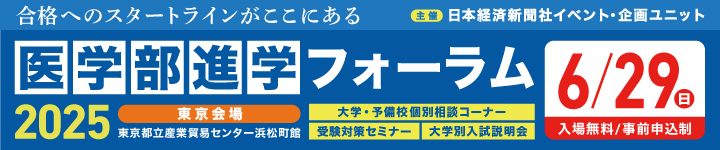お知らせ
(2)S-ICDの利点から見た適応・不適応例[特集:完全皮下植込み型除細動器(S-ICD)の仕組み]

完全皮下植込み型除細動器(S-ICD)システムは,皮下に留置されるS-ICDリードとパルスジェネレータから構成される
S-ICDの不整脈の感知,検出には皮下心電図が用いられ,センシング不全や不適切作動の予防のため,適応選択の際には植込み型除細動器(ICD)適応に加え,術前スクリーニング適合が必要となる

S-ICDはICD適応を有するが,ペーシングの適応〔徐脈,抗頻拍ペーシング(ATP),心臓再同期療法(CRT)〕を有さない場合,血管アクセスの困難な場合,感染リスクの高い場合に推奨される
1. わが国における植込み型除細動器(ICD)の現況
植込み型除細動器(implantable cardioverter defibrillator:ICD)は,致死的心室性不整脈による心臓突然死(sudden cardiac death)を回避する,最も確立された治療法である。ICDは不整脈停止効果のみならずデバイスの高機能化,さらにショックリダクションをはじめとする洗練された治療ストラテジーの確立により,一次予防,二次予防を問わず,心臓突然死予防の標準的治療となっている。一方,リード関連合併症やデバイス感染など,長期安全性の確立は依然としてICD治療における大きな課題である。
わが国では2014年から着用型自動除細動器(wearable cardioverter defibrillator:WCD)が,2016年2月から完全皮下植込み型除細動器(subcutaneous ICD:S-ICD)が臨床使用可能となった。これら新型デバイスの共通点は,いずれも非血管内留置型かつ恒久的ペーシング機能を有さない,ショック治療のみのデバイスであるという点であり,リード留置による血管(心腔)内除細動を基本とする従来のICDは,経静脈植込み型除細動器(transvenous ICD:TV-ICD)として現在ではS-ICDと明確に区別されている。