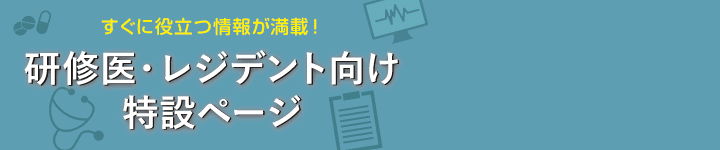お知らせ
志賀直哉の『赤西蠣太』と『城の崎にて』─日本人が理想とする人間像[エッセイ]
志賀直哉が1917(大正6)年に発表した『赤西蠣太』と『城の崎にて』には、日本人が理想とするような人物ないしは心情が描かれている。
『赤西蠣太』
大正6年9月に志賀直哉が発表した『赤西蠣太』は、容貌上のハンディを持つ武士を主人公とした作品である。

この物語の主人公・赤西蠣太は、仙台坂にある伊達兵部の屋敷に勤める侍だが、彼は、「三十四、五だというが、老けていて四十以上に誰の眼にも見えた」、「容貌は所謂醜男の方で言葉にも変な訛があって、野暮臭い何処までも田舎侍らしい侍だった」と書かれているように、甚だ風采の上がらぬ男だった。
また、蠣太は、「真面目に独りこつこつと働くので一般の受けはよかった」ものの、特に働きのある人物とも見えなかったので、若者達は彼を馬鹿にして、何かと利用するようなこともあった。しかし、そういう時にも、蠣太は怒りもせず平気で利用されていたため、そのうち彼を馬鹿にする者はいなくなった。
一人者の蠣太は、酒を飲むでも女遊びをするでもなく、非番の日などは一人で将棋を指していたが、そんな蠣太が、ある密命を帯びて逐電することになる。しかし、ただいなくなったのではその意図を怪しまれるので、友人の入れ智恵で、女性にふられて面目を失ったために夜逃げをしたという形をとることにした。その酒好き女好きの美男の友人は、「君の顔でやればそれに間違いなく成功する」と断言したのである。
そこで蠣太は、屋敷でも「なるべく美しい、そして気位の高い女」に付け文をした。蠣太の書いた艶書は、「妙に真面目で如何にも艶も味もない」ものだったが、案に相違して、その女性からの返事は好意的なものだった。かねてより蠣太のことを尊敬していた彼女は、自分が求めていたのは蠣太の「内にあるもの」で、「美しい若侍方に何となくあきたらなかったのは、そういうものが若侍方の内にない」ことに気づいたというのである。
その返書を読んだ蠣太は、夢のような気持ちになって赤面すると同時に、「自分は人間の最も聖い気持を悪戯に使おうとした」と、いたたまれない気持ちになるのだが、このように見てくると、『赤西蠣太』は、主人公が容貌上のハンディを持つという点では、前年の1916(大正5)年に発表された芥川龍之介の『鼻』を思わせる作品でもある。ただ、『鼻』の主人公の高僧・禅智内供が、長い鼻のことを気にしないふりを装いながらも、内心では常に鼻のことを気にしていたのとは違って、蠣太は、醜男ゆえに傷つきながらも、そのことをそれほど気に留めていない。
蠣太は、身体的なコンプレックスが及ぼす影響の少なさという点においては、人間としての格が禅智内供より上とも言えるが、醜男が優れた人間性ゆえに美女から好かれるという設定には、エドモン・ロスタンが1897年に発表した『シラノ・ド・ベルジュラック』を想起させるものがある。あるいは蠣太の場合も、あたら美男に生まれなかったがゆえに内面を磨きえたという事情があったのかもしれないが、そうした事情とは別に、蠣太が体現しているような、真面目で、外見や周囲の評価に振り回されず、黙々と自らの使命を果たすものの、恋愛や処世には控え目で不器用という人間は、我々日本人が理想とする人間像のひとつではあるまいか?
『城の崎にて』
『赤西蠣太』の4カ月前の大正6年5月に発表された『城の崎にて』には、多くの日本人が理想とするような心境が描かれている。
「山の手線の電車に跳飛ばされて怪我をした」主人公は、医師から「背中の傷が脊椎カリエスになれば致命傷になりかねないが、そんな事はあるまい」、「兎に角要心は肝心だから」と言われる。そのため、但馬の城崎温泉に3週間ほど逗留した彼は、そこでそれまで感じたことのないような死生観を得ることになる。
当時の主人公は、事故の後遺症で、「頭は未だ何だか明瞭しない。物忘れが烈しくなった」というような状態だったが、「気分は近年になく静まって、落ちついたいい気持がしていた」。たとえば、「一つ間違えば、今頃は青山の土の下に仰向けになって寝ている所だった」と思う一方で、「それは淋しいが、それ程に自分を恐怖させない考だった」、「妙に自分の心は静まって了った。自分の心には、何かしら死に対する親しみが起っていた」と語るのである。
これは、動物の死に直面したときも同様で、屋根の上に蜂の死骸を見たときにも、「冷たい瓦の上に一つ残った死骸を見る事は淋しかった。然し、それは如何にも静かだった」、「自分はその静かさに親しみを感じた」と言っている。また、自分の投げた石に当たって河原のイモリが死んだときには、「可哀想に想うと同時に、生き物の淋しさを一緒に感じた」として、事故に遭いながらも死ななかった自分と、まったくの偶然で不意に死んでしまったイモリを比較して、次のように感じている。「自分はそれに対し、感謝しなければ済まぬような気もした。然し実際喜びの感じは湧き上っては来なかった。生きている事と死んでしまっている事と、それは両極ではなかった。それ程に差はないような気がした」。
ここに描かれているような静謐で落ち着いた心境や、死に対する親しみの感情、生死一如という考え方などは、多くの日本人が、あろうことなら自分もそうありたいと願う境地ではあるまいか? 『城の崎にて』は、こうした日本人が共感しやすい境地を描いた作品なのであって、『赤西蠣太』にせよ『城の崎にて』にせよ、日本人が理想とする境地や人物を描いたところに、志賀直哉という作家が国民的な支持を得てきた理由のひとつもあると思われるが、ここで忘れてならないのは、主人公がこのような境地に到達した背景には、一歩間違えれば死んだかもしれない事故に遭っているという事実があるということである。
この主人公は、命に関わりかねないほどの事故に遭ったればこそ、透徹した死生観を得られたということもできるのではあるまいか。もっとも、当時の主人公が、「頭は未だ何だか明瞭しない」と、健忘を伴う精神変調をきたしていたという記述をみると、彼が到達した静穏な心境というのも、そうした外傷後の一過性の脳機能障害によるものだったのかもしれないが、いずれにしてもそこには、人生に新たな転機や認識をもたらすものとしての病が描かれている。