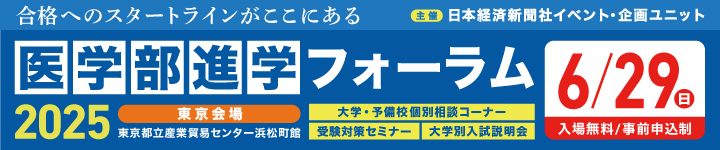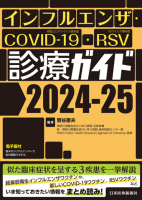お知らせ
Chlamydia trachomatis治療におけるアジスロマイシンの有効率低下の原因と治療薬【有効性は低下せず,維持されていると考えるのが妥当】

非淋菌性尿道炎の代表的な原因菌であるChlamydia trachomatisの治療は同菌に抗菌力を有するマクロライド系,テトラサイクリン系およびフルオロキノロン系抗菌薬が推奨され,薬剤耐性菌はほとんど存在しないとされています。ところが最近,アジスロマイシンの有効率が低下しているとの報告が散見されます。これは耐性菌が存在し増加していることが原因と考えてよいでしょうか。また,今後治療薬はどうすればよいでしょうか。
札幌医科大学・髙橋 聡先生にご解説をお願いします。
【質問者】

安田 満 岐阜大学医学部泌尿器科講師
【回答】
尿道炎の原因微生物としては,淋菌とC. trachomatisが最も検出頻度が高く,性感染症として問題になっています。淋菌性尿道炎の原因微生物である淋菌は世界的に抗菌薬に対する多剤耐性化が進んでおり,従来は有効であった経口抗菌薬の感受性が低下するなど問題となっています。一方,C. trachomatisは,非淋菌性尿道炎において最も検出頻度の高い病原微生物です。C. trachomatisの抗菌薬感受性を検討した報告1)では,抗菌薬に対する耐性傾向は認められませんでした。
クラミジア性尿道炎に対する治療は,いくつかの有効な抗菌薬によりますが,単回投与で有効なアジスロマイシンは,その中でも飲み忘れや飲み残しがないことから,服薬のコンプライアンスの面でも優れています。アジスロマイシンについては,臨床分離株での抗菌薬感受性の低下も認められていません。

残り739文字あります
会員登録頂くことで利用範囲が広がります。 » 会員登録する