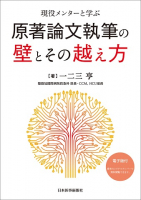お知らせ
■NEWS 【欧州心臓病学会(ESC)】AFアブレーション後1年間再発なしでOAC中止可能?:RCT"ALONE-AF"
心房細動(AF)に対するカテーテルアブレーションの成績は、改善されつつある。しかしアブレーション成功例において経口抗凝固薬(OAC)を中止できるや否やについては、各国ガイドラインを含め、まだコンセンサスがない。しかし患者からすれば、「せっかくアブレーションを受けてAFが治ったのになぜ、出血リスクのある薬剤を続けなければならないのか」という不満は残るだろう。
8月29日からマドリッド(スペイン)で開催された欧州心臓病学会(ESC)学術集会では、AFアブレーション成功例におけるOAC中止の安全性を検討したランダム化比較試験(RCT)"ALONE-AF"が、韓国・延世大学のBoyoung Joung氏により報告された。

良好な結果となったが、細かく見ると疑義も生じる結果だった。
【対象】
ALONE-AF試験の対象は、AFアブレーション施行後1年間、「AF再発」を認めなかった韓国在住840例である。CHA2DS2-VAScスコア「0」男性、「≦1」女性は除外されている。「AF再発」は「24~72時間ホルター心電計」で確認した。なお全例、OACを服用している。
平均年齢は64歳、男性が75%を占めた。AFは68%が「発作性」、CHA2DS2-VAScスコア中央値、HAS-BLEDスコア中央値はいずれも「2」だった。またアブレーションは87%が「ラジオ波焼灼術」だった。全例「肺静脈隔離術」である。
【方法】
これら840例はOAC「継続」群と「中止」群にランダム化され、非盲検下で2年間観察された。
【結果】
その結果、1次評価項目である「脳卒中・全身性塞栓症・大出血(ISTH基準)」発生率はOAC「中止」群で「継続」群に比べ、1.9%の有意低値となっていた(P=0.02)。2年間の治療必要数(NNT)は「53」である。
両群間の差が著明となったのは「大出血」だった(「中止」群:0% vs.「継続」群:1.4%)。ただし、両群のカプランマイヤー曲線間の差が大きく開くのは、試験開始後18カ月以降だった。一方、「脳卒中・全身塞栓症」の発生率には両群間で有意差を認めなかった(0.3 vs. 0.8%)。
亜集団解析の結果、OAC「中止」群における「脳卒中・全身性塞栓症・大出血」リスク減少は「AF類型(発作性 vs. 持続性)」だけでなく、「CHA2DS2-VAScスコアの高低」や「HAS-BLEDスコアの高低」を問わず、認められた(有意な交互作用を認めず)。
【考察】
さて「脳卒中・全身塞栓症」発生率は、有意差に至らないとはいえ、OAC「継続」群で「中止」群に比べ高かった。奇妙ではないだろうか。
この点に疑義を呈したのが、エレブルー大学病院(スウェーデン)のMadelene Carina Blomstrom-Lundqvist氏である。同氏は、ランダム化時点ですでに、OAC「継続」群のほうが「脳卒中・全身塞栓症」高リスクだった可能性を指摘した。具体的には「AF burden」(心房細動負荷:心電計測定時間に占めるAF出現時間の割合)の群間不均衡の可能性である。ALONE-AF試験では開始時の「AF burden」が評価されていない。
AF burdenは近時、その高値に伴い脳卒中や心不全リスクが上昇するため、新たなリスク因子として注目されている[2023年総説]。
ALONE-AF試験は韓国政府機関と三真製薬から資金提供を受けた。また報告と同時に論文が、JAMA誌ウェブサイトで公開された。