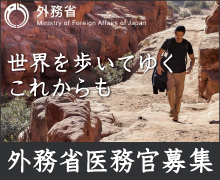お知らせ
■NEWS 意思決定支援の取り組みに対する評価のあり方を議論─入院・外来医療等分科会
診療報酬調査専門組織の入院・外来医療等の調査評価分科会は7月31日、「地域包括診療料・加算」等の施設基準で求められる患者の意思決定支援(ACP)を巡り議論した。委員からは、患者の転院に対応できるよう施設間の情報共有を進めるべきだとする意見や、患者・家族の満足度などに基づくアウトカム評価の導入を提案する意見が示された。
2024年度診療報酬改定では、入院通則の改定によって厚生労働省の「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」等の内容を踏まえた適切な意思決定に関する指針の策定を原則、すべての入院料で要件化。外来の「(認知症)地域包括診療料・加算」の施設基準にも指針の策定が追加された。

厚労省のデータで入院における対応状況をみると、24年11月時点で指針を作成していた医療機関は80.3%。外来について指針を作成していた病院は84.0%、診療所は19.6%だった。また、「地域包括診療料」の届出医療機関の指針作成率は70.1%、「地域包括診療加算」の届出医療機関では41.5%となっていた。
■施設間の情報共有推進やアウトカム評価の導入を求める意見も
議論では中野惠委員(健康保険組合連合会参与)が、患者が意思決定に至るまでの話し合いなどに加え、患者の転院時、転院先に情報提供することまでを一連の対応として支援する仕組みづくりが必要であると指摘。津留英智委員(全日本病院協会常任理事)は、「現在は取り組みをしていなければ(入院料等の)届出ができないペナルティの評価になっているが、意思決定支援の効果についてプラスの評価を検討してもいいのではないか」と述べ、患者のQOL向上への貢献度や患者・家族の満足度などを指標とした具体的なアウトカム評価の導入を提案した。
今村英仁委員(日本医師会常任理事)は、「今の医療機関に押し付けられているような形、医療機関側が家族にACPの指導をして強制的に進めざるを得ない状況は方向性として正しいのか懸念がある」と述べ、国や保険者のより積極的な関与を求めた。