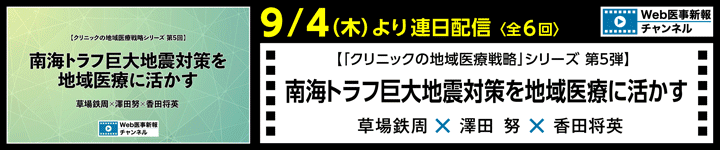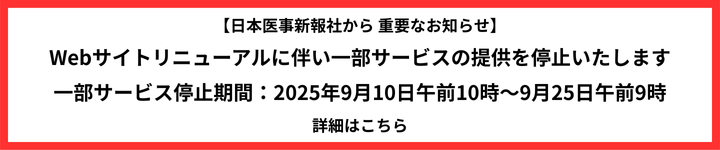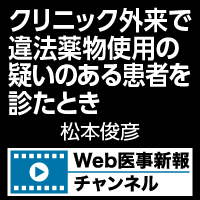お知らせ
【OPINION】健康問題としての薬物依存症─薬物依存症からの回復のために医療者は何ができるか

近年、芸能人の覚せい剤事件がしばしばマスメディアを騒がせています。そのたびにテレビのワイドショー番組は、「転落への道」とか「心の闇」などと題した、その芸能人の経歴に関するゴシップ情報をひっきりなしに取り上げ、最後に、識者が薬物犯罪の厳罰化を唱えるとともに、その芸能人に「反省を求める」といった趣旨の言葉で番組は締めくくられます。もはやワンパターンといってもよい、“ベタ”な番組構成です。

しかし、こうしたベタな報道は、健康問題の専門家である医療者にも、無視できない影響を与えている気がします。実際、私の印象では、いまだに医療者の中には、薬物犯罪はあくまでも刑罰の対象であって、医療の対象外と考える人が少なくありません。尿検査などで違法薬物使用者を発見した場合には、医療者として何らかの助言もしないまま、単に警察に通報することだけが「医療者の良心、責務」と信じて疑わない人もいます。
しかし、本当にそれでよいのでしょうか。薬物問題には犯罪としての側面だけでなく、薬物依存症という健康問題としての側面もあります。本稿では、この後者の側面について医療者としてどう捉え、どう対応していくべきなのかについて、私見を述べさせていただきたいと思います。
薬物依存症は罰では治らない
最初に昔話からはじめましょう。
数年前、刑務所で薬物乱用離脱プログラムの講師を務めたときの話です。そのとき私は、受刑者たちに、「覚せい剤をやめられず、親分やアニキからヤキを入れられたことがある人、挙手して」と質問しました。
すると、間髪おかずに全員が手を挙げました。まあ、あたりまえでしょう。依存症という病気は、本人よりも先に周囲を悩ませ、苛立たせます。
続けて私は「ヤキを入れられてどんな気分になったか」と聞いてみました。今度は全員が黙り込みました。しかし、しばしの気まずい沈黙の後、1人の受刑者が意を決したように口を開いてくれました。「余計にクスリをやりたくなった」。この発言に受刑者全員が一様に肯いた光景を今でも覚えています。
この質問は完全に確信犯的なものでした。私は、自らの臨床経験から、再使用によって最も失望しているのは、誰よりも薬物依存症者自身であることをよく知っていました。問題は、依存症に罹患した脳は、自己嫌悪やみじめさ、恥ずかしさを自覚した瞬間に、「シラフじゃいられない」と渇望のスイッチがONになってしまうことです。なかには、「こんな自分は消えた方が世の中のためだ」などと考え、死のうとしていつもの何倍もの覚せい剤を注射する者もいます。「余計にクスリをやりたくなった」とは、要するにそういう意味なのです。それで、結局また覚せい剤を使ってしまうわけです。
いかなる理由からであれ、薬物を使えば使った分だけ進行するのが依存症です。その意味では、善意から「ヤキを入れた」はずなのに、その結果は皮肉にも依存症をさらに重症化させたともいえるでしょう。
このエピソードが意味するのは、薬物依存症は罰では治らないという事実です。

残り5,512文字あります
会員登録頂くことで利用範囲が広がります。 » 会員登録する