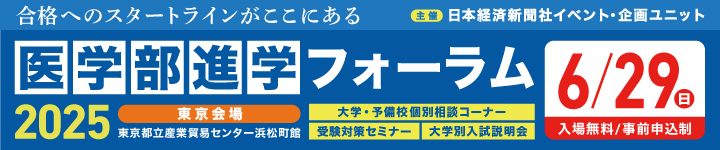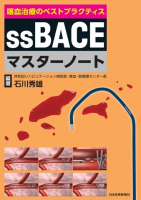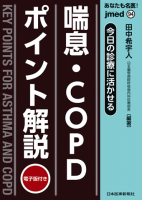お知らせ
特発性肺線維症に対するわが国初の治療ガイドライン

【抗線維化薬などの限られた薬剤をいかにしてうまく使用していくか問われる時代に】
特発性肺線維症(IPF)は,高度の線維化が慢性進行する原因不明の肺疾患で,わが国の指定難病に含まれる。特定疾患登録を起点にしたわが国の報告では,IPF患者の生存期間中央値は35カ月であり,その死因は原疾患進行に伴う慢性呼吸不全,急性増悪,肺癌が75%を占め1),その対策が長年の課題であった。2008年にはピルフェニドン,15年にはニンテダニブの抗線維化薬が承認され,同年にupdateされたIPF治療に関する国際的な実臨床ガイドライン2)において,使用を提案すべき薬剤と位置づけられた。そして,17年2月にわが国のIPF治療ガイドライン(『特発性肺線維症の治療ガイドライン2017』)の発刊に至った。

本ガイドラインでは,慢性安定期における薬物/非薬物療法,急性増悪,肺癌合併の対応が17のクリニカルクエスチョンから構成されており,その回答にはエビデンスの質と推奨の強さが示されている。この,わが国初の治療ガイドラインによって,IPFという難病に対する治療選択の新たな時代が始まった。ガイドラインの普及を願うとともに,さらなるエビデンスの蓄積によって今後の改訂ガイドラインにつながることを期待する。
【文献】
1) Natsuizaka M, et al:Am J Respir Crit Care Med. 2014;190(7):773-9.
2) Raghu G, et al:Am J Respir Crit Care Med. 2015;192(2):e3-19.
【解説】
山内浩義*1,萩原弘一*2 自治医科大学呼吸器内科 *1講師 *2教授