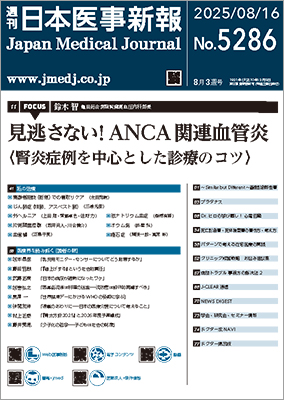お知らせ
【識者の眼】「かかりつけ医機能報告制度」小野 剛
小野 剛 (市立大森病院院長、一般社団法人日本地域医療学会理事長)
登録日: 2025-08-19
最終更新日: 2025-08-13
高齢化が進む中で、複数の慢性疾患、医療と介護の複合ニーズをかかえる高齢患者が多くなるとともに、自宅や施設で最期を迎える患者も多くなってきた。これからは、「治す医療」から「治し支え、寄り添う医療」への転換が必要であり、医療・介護連携を柱とした地域包括ケアの取り組みと過不足のない医療提供体制の構築が求められている。地域住民に健康上の問題が発生したときに、住み慣れた地域で適時適切に対応してもらえる「かかりつけ医」の存在は、今後の地域医療提供体制の中で必要である。地域住民が自分のニーズに合った医療機関を上手に選択し、継続して通院するためには、地域における「かかりつけ医」の情報をわかりやすく提供することが重要と考える。
「かかりつけ医」については、2013年に日本医師会・四病院団体協議会合同提言で「なんでも相談できる上、最新の医療情報を熟知して、必要な時には専門医、専門医療機関を紹介でき、身近で頼りになる地域医療、保健、福祉を担う総合的な能力を有する医師」と定義された。その後、『経済財政運営と改革の基本方針2015』に「かかりつけ医の普及の観点からの診療報酬上の対応や外来時の定額負担について検討する」と記載された。さらに議論を重ね、2023年5月に「全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律」が成立し、2025年4月から「かかりつけ医機能報告制度」が施行されている。2026年1月には、医療機関からの初回報告が実施される予定となっている。

その報告の主な内容は、日常的な診療(17領域40疾患)を総合的かつ継続的に行う機能(1号機能)と、4つの機能〔①通常の診療時間外の診療、②入退院の支援、③在宅医療の提供、④介護サービス等と連携した医療提供(2号機能)〕で構成され、1号機能を有する医療機関が2号機能に係る報告を行う建てつけになっている。今後、各医療機関からの報告が開始されるが、耳鼻咽喉科や眼科など、その診療科目に特化した医療機関はどのように報告すべきなのか、地域で報告を行う医療機関と行わない医療機関が混在することで地域住民は混乱しないのか、などについて懸念している。
「かかりつけ医機能」は慢性疾患を有し、継続的な医療を必要とする患者を地域で支えるために確保すべき機能で、夜間・休日対応、在宅患者の24時間対応、後方支援病床の確保なども含まれるが、地域によっては不足する機能もありうる。そのため、不足する機能をどのように確保するかが重要であり、地域における協議の場で調整することが求められる。高齢化社会では医療だけでなく、介護ニーズ、さらには福祉ニーズも持ち合わせる患者も多く、介護部門や行政を含めた多職種連携と地域包括ケアの観点からの協議を期待している。
10年以上の議論を経て新たな制度がスタートしたが、この制度を有意義なものにするためにも地域における総合診療医の活躍が必要であり、何よりも地域住民のウェルビーイングにつながる制度になることが求められている。
小野 剛(市立大森病院院長、一般社団法人日本地域医療学会理事長)[治し支え寄り添う医療][総合診療医]