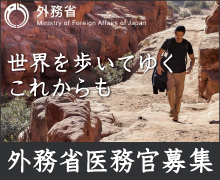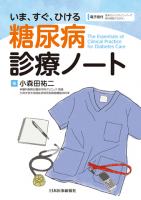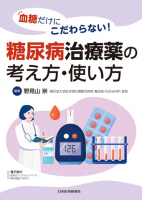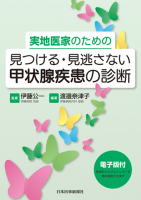お知らせ
■NEWS 「アクチビンB」が糖代謝制御する仕組みを発見─JIHS・東大などの研究グループ
国立健康危機管理研究機構(JIHS)は4月24日、東大、ドイツ・ライプツィヒ大との国際共同研究で、肝臓由来のタンパク質「アクチビンB」が糖代謝を改善する新たな仕組みを発見したと発表した。糖尿病のあらゆる病態を改善できる治療薬の開発につながる研究成果として注目される。
アクチビンBは、TGF-βスーパーファミリーに属するサイトカインの一種アクチビンのサブファミリーの1つ。 国際共同研究を進めたJIHS糖尿病研究センターの植木浩二郎センター長、JIHS分子糖尿病医学研究部の小林直樹上級研究員らのグループは、アクチビンBを過剰発現させた肥満マウスモデルで、耐糖能の改善、インスリン感受性の向上、グルコース応答性インスリン分泌の亢進を確認。

その作用メカニズムを検索した結果、アクチビンBは、肝臓でFGF21の産生を促進しインスリン感受性を高める一方で、肝臓のグルカゴンに対する反応性(グルカゴン感受性)を低下させることで血糖を改善する仕組みを持つことが明らかになった。
■糖尿病のあらゆる病態改善できる治療薬開発の可能性
JIHSは、FGF21の誘導とグルカゴン感受性の制御を通じた二重の作用は「従来の薬剤では困難だった病態の同時制御を可能にする可能性がある」と説明。「肝臓でアクチビンシグナルを活性化する薬剤を開発できれば、1剤で糖尿病のほぼすべての病態を改善できる治療法を実現できる可能性がある」としている。