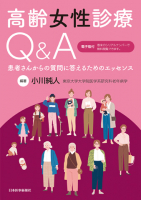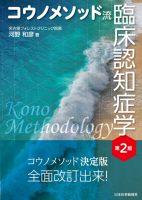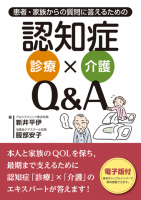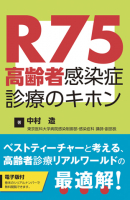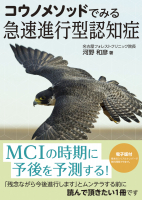お知らせ
【識者の眼】「地域包括ケア時代の高齢者就労とその多面的意義④─生きがいを実感できる仕事とは」藤原佳典

これまで述べたように、高齢期就労による健康効果を高めるには、収入もさることながら生きがいを実感できることが重要である。筆者は、多くの働く高齢者にインタビューしてきた。その中で共通するのは、「周囲から直接感謝される、人や社会の役に立っている」という社会貢献と、「自分自身のためになっている、面白い、達成感」といった自己実現に類する声である。
それでは、高齢期において生きがいを実感しやすい就労についてはどのような理論基盤に基づき考えればよいのであろうか。「人間は自己実現に向かって絶えず成長する生きものである」と提唱したマズローは、人間の行動の源となっている欲求が、生理的欲求(第一段階)、安全と安心の欲求(第二段階)、所属と愛の欲求(第三段階)、 自尊心や承認の欲求(第四段階)、自己実現の欲求(第五段階)の階層性をもつことを示した。就労の主な動機に当てはめると、 貧困の回避という意味で、金銭目的が生理的欲求(第一段階)に相当する。一方、生きがいを追求する就労は、社会貢献を通した自尊心・承認の欲求(第四段階)と自己実現の欲求(第五段階)に相当すると考えられる。

筆者は2024年以降、産官学民の有識者による高齢者就労支援に関する研究会ESSENCE(Employment Support System for Enhancing Community Engagement)を主宰している。同研究会においては、多くの事例を繙きながら、高齢者が長期にわたり生きがいを実感し、安心して継続できる就労とはどのようなものかについて検討してきた。その1例として、介護・福祉の分野における就労が挙げられた。
わが国の介護人材不足が、きわめて危機的な状況に直面していることは言うまでもない。第8期介護保険事業計画の介護サービス見込み量等に基づき、2021年7月9日に都道府県が推計した介護職員の必要数が公表された。それによれば、2025年度には介護職員の必要数である約243万人を満たすには、約32万人(5.3万人/年)の増強が必要である。その傾向はさらに深刻化し、2040年度には約280万人の必要数に対して約69万人(3.3万人/年)の介護職員を新たに確保する必要があると推計されている。
介護・福祉分野の有効求人倍率は、他産業の水準を大きく上回っている。2021年に厚生労働省が公表した、介護職員の有効求人倍率は3.6倍であった。他産業の有効求人倍率が1.13であることを考慮すると、介護業界の人材不足が実感できる。
一方、在留資格「技能実習」に関わる在留者数は2022年6月末時点で総数32万7689人であるのに対して、介護分野では1万5011人にすぎない。介護のデジタル化やロボットによる生産性の向上が促進されているものの、わが国は小規模の介護事業所が多く、いまだ未着手の事業所も少なくない。こうした状況の打開策の1つとして、期待されるのが高齢者を主力とする「介護助手」である。次回にて「介護助手」の実態と効果について、紹介したい。
藤原佳典(東京都健康長寿医療センター研究所副所長)[高齢者就労][健康]