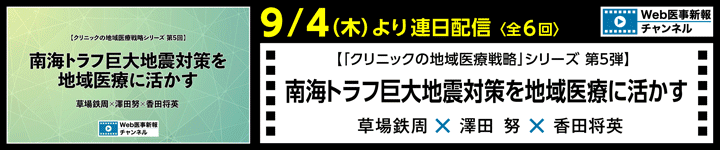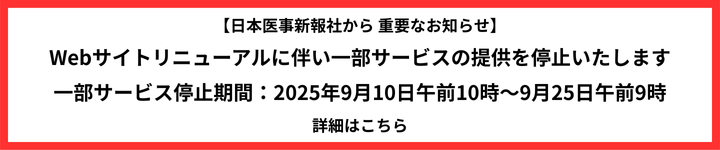お知らせ
【識者の眼】「パンデミックの海で⑬─現代楢山節考(上)」櫻井 滋
大都会の事情を詳細には知りえない筆者だが、少なくとも地方都市では新型コロナウイルス感染症(COVID-19)について、介護福祉施設においてクラスターが猛威を振るうパンデミック3年目の冬(2022年1〜3月)があった。
多数の高齢者が半ば当然のごとくコロナの犠牲になり、もはや死者はただの数値とされたかのようであった。そればかりか、警戒感を煽る社会の雰囲気をあざ笑うかように数多くの施設で繰り返しクラスターが生じた。

一般的には地域封鎖を意味する「ロックダウン」と称して、肉親との面会はおろか施設への新規入所までも厳しく制限して集団としての隔離期間終了を待つうちに、再び感染が広がる施設もあった。臨床疫学的には1つ目のクラスターと2つ目のクラスターの開始・終了時期がつまびらかでないほど、流行を繰り返す施設も見られた。このような施設には外部専門家による感染対策指導が行われ、施設側も保健所の指示に真摯にしたがったのであるが、流行は繰り返し生じた。
そのような状況が生じた背景には、職員を端緒とする施設内流行があることは明らかだった。しかし、職員に対して院内での感染予防を指導したとしても、その家族や幼い子どもたちに医療関連施設レベルの感染対策を課すことは困難であるばかりか、そもそも社会には感染対策を家庭に持ち込む覚悟も備えもなかった。ウイルスはクルーズ船のような集団感染の場や医療機関クラスターから空気に乗って渡来するのではなく、むしろ社会から医療機関のバックドアを通って持ち込まれた。
もとより、医療機関における「隔離」とは患者を捨て置くことではない。隔離は「保護」でなければならない。そればかりか不要不急の医療行為でない限り、パンデミックの間も診断や治療の継続が求められた。しかし、実態が期待とは異なっていたことは当連載の初期で触れた通りである。
ウイルスに対する恐怖は、従事者が意識するか否かとは別に医療的介入の時期を遅らせ、診療機会を減らしていた。皮肉なことに、医療的介入の頻度を低くすれば感染のリスクは減少する。もしも診療開始時期が多少遅れ、あるいは介入がなされなかったにもかかわらず、患者の予後が変わらないとすれば、むしろ平時の医療の意義が問われかねない。
流行初期において、公衆衛生の専門家が思い描いていた戦略は新型インフルエンザウイルスへの対策と同様のスキームである。まずは水際で国内への侵入を最小限にした上で、国内での感染例は少数のうちに隔離施設に収容し、隔離が困難になった時点では自宅等にとどまるよう行動制限を強化し、あるいは地域を封鎖するなどして「国内蔓延を阻止する」というものである。
今般のパンデミックは予測されたシナリオではあるものの、極めて急速に進行した。それぞれの段階を実施しつつも、不十分なままに国内蔓延期に入った。いくつかの地方では蔓延抑制効果が見られたが、危機的な経済状況を要因として国が蔓延状態を受け入れ、行動制限を撤廃するとともに全国的蔓延状態は既成事実となり、国民の「クラスター慣れ」を生む状況へと移行した。
当初は対岸の火事ととらえていた地方自治体も、早晩大火を経験することとなった。問題は、それらのウイルスの拡散が教育機関や家庭を介して、医療従事者の職場である医療機関で蔓延する事態となり、さらには面会謝絶をあざ笑うかのように福祉施設に入り込み、高齢者を襲ったことである。(続く)
櫻井 滋(東八幡平病院危機管理担当顧問)[介護福祉施設でのクラスター発生]