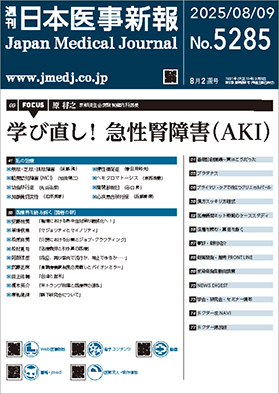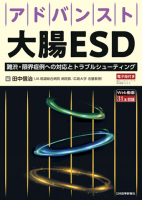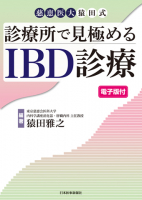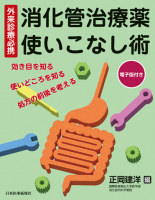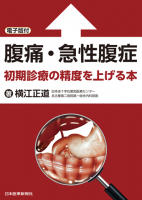お知らせ
慢性便秘症[私の治療]

わが国の2016(平成28)年度の国民生活基礎調査によると,便秘の有訴者数は2~5%程度と言われている。男性(2.5%)よりも女性(4.6%)に多い傾向を示しており,加齢により有病率が増加している。しかしながら,慢性便秘症に限定した疫学調査は行われていないのが現状である。
▶診断のポイント
日本での便秘の診療の基本となっている「慢性便秘症診療ガイドライン2017」1)では,「本来体外に排出すべき糞便を十分量かつ快適に排出できない状態」と定義されている。一方,海外では,2016年に発表されたRome Ⅳ基準の中で機能性便秘の定義を,排便困難,排便回数が少ない,または排便が不完全であるといった有症状の機能性腸疾患としている1)。

▶私の治療方針・処方の組み立て方
従来治療薬とされる酸化マグネシウムを第一選択薬として使用する。この際注意すべきことは,高齢者や糖尿病患者のように腎機能が低下している場合には,高マグネシウム血症のリスクがあるため,減量ないしは他剤から投与する。酸化マグネシウム使用にあたっては,多くのガイドラインや当局指針が血中マグネシウム濃度の測定を勧告しているため,定期的血液検査を行う。
酸化マグネシウム投与では改善しない場合や腎機能低下で使いにくい場合は,新規便秘症治療薬とされるルビプロストン,リナクロチド,エロビキシバット,ポリエチレングリコール,ラクツロースなどを,各薬剤の特徴を考えながら第二選択薬として処方する。以上の新薬はどれを選べばよいかのエビデンスには乏しいので,効果をみながら無効な場合は間髪を入れずに別の新規薬剤に切り替えて反応をみる。
各種新薬でも効果不十分である場合に限り,刺激性下剤を用いる。刺激性下剤は,精神依存や長期乱用となる可能性が高く頓用使用にとどめることが重要である。坐薬や浣腸などの経肛門的処置をする場合は,腹部エコーや直腸指診を行い,直腸に糞便塞栓があるかの診断を行い,硬便による糞便塞栓ありの場合は,浣腸などを使う前に丁寧に摘便を行うことで腸管穿孔のリスクが減らせる。

残り1,043文字あります
会員登録頂くことで利用範囲が広がります。 » 会員登録する