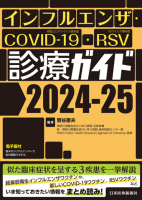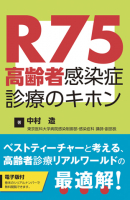お知らせ
インフルエンザの実際の全罹患者数,定点報告数の何倍になる?
インフルエンザに関しては定点報告となっています。実際のわが国全体の罹患者数に関しては,定点報告数のおよそ何倍と考えたらよいのでしょうか。(千葉県 K)
【回答】
【“何倍”と推定することは難しい。実態をより反映できる計算法で,全数を推定している】

定点報告数をもとに実際の罹患者数を推定することは可能ですが,“何倍になるか”を推定することは難しいものです。定点報告数に関係する項目として,①全数把握と定点把握,②定点医療機関の決め方,③定点当たり報告数のメリットとデメリット,④全数(実際の罹患者数)の推定,について解説します。
【①全数把握と定点把握】
感染症法に基づいて報告される感染症は,全部で113種類(2023年5月18日現在)あり,疾患の重篤度や感染経路などから,1~5類,新型インフルエンザ等感染症,に分類されています。
このうち,1~4類までのすべてと,5類のうちの24種類,新型インフルエンザ等感染症(2023年5月18日時点では,該当なし)の合計87種類は「全数把握対象疾患」といい,すべての医療機関に報告義務があります。
残りのインフルエンザといった26種類の感染症は「定点把握対象疾患」といいます。これらについては,医療機関の中から選定され,調査に協力して頂いている「定点医療機関」からのみ報告されます1)。
【②定点医療機関の決め方】
定点医療機関の選定方法は,国が定めた「感染症発生動向調査事業実施要綱」の中で,以下のように規定されています1)。
・関係医師会等の協力を得て,医療機関の中から可能な限り無作為に選定する。
・人口および医療機関の分布等を勘案して,できるだけ当該都道府県全体の感染症の発生状況を把握できるよう考慮する。
インフルエンザは,インフルエンザ定点医療機関(全国約5000箇所の内科・小児科医療機関),および基幹定点医療機関(全国約500箇所の,内科および外科の診療科を持つ300床以上の医療機関)から報告されます。
【③定点当たり報告数のメリットとデメリット】
「定点当たり報告数」とは,対象となる感染症について,すべての定点医療機関からの報告数を定点医療機関数で割った値のことで,1医療機関当たりの平均報告数のことです。ほかの地域や全国レベルで流行状況を比較する場合などに有効です。
一方,定点医療機関の数は限られているので,各地域の流行状況を評価するのに十分な数とはなりません。また,各医療機関の規模や診療科目の違いなどによって,患者数や患者の年齢構成がかなり異なっている可能性もあります。
【④全数(実際の罹患者数)の推定】
従来,インフルエンザの全数の推定は,「医療機関の施設数」(定点当たり報告数×全医療機関の施設数)を用いていましたが,医療機関の規模が適切に反映されず,推計が過大となる傾向が指摘されていました。そのため,2018/19シーズンからは,実態をより反映できるように「外来患者延べ数」を用いた推定方法〔(定点医療機関からの報告数を,定点医療機関の外来患者延べ数で割った値)×全医療機関の外来患者延べ数〕に変更となりました。
◎
なお,2021/22シーズンは前シーズン同様に,報告数は非常に低調で,シーズンを通して明確なピークは形成されませんでした2)。
【文献】
1)厚生労働省:感染症法に基づく医師の届出のお願い.
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/kekkaku-kansen shou/kekkaku-kansenshou11/01.html
2) 国立感染症研究所, 厚生労働省健康局結核感染症課:今冬のインフルエンザについて(2021/22シーズン). 2022.
https://www.niid.go.jp/niid/images/idsc/disea se/influ/fludoko2022.pdf
【回答者】
石金正裕 国立国際医療研究センター病院 国際感染症センター/ AMR臨床リファレンスセンター/ WHO協力センター