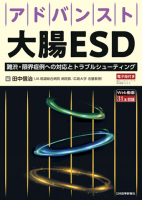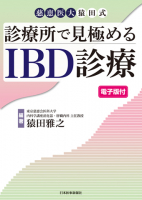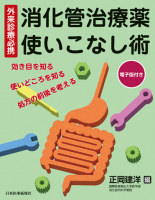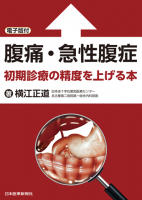お知らせ
炎症性腸疾患(IBD)における治療の進歩と展望

【抗TNFα抗体製剤の登場以降,選択の幅が広がっている】
炎症性腸疾患(IBD)は,消化管に原因不明の炎症をきたす潰瘍性大腸炎(UC)とクローン病(CD)を総称して呼び,厚生労働省の指定難病となっている。若年者に好発し,患者は慢性的な腹痛,下痢,血便などの症状により日常生活,社会活動に大きく影響を受ける。免疫などに関わる遺伝子の変異や,腸内細菌を含めた腸管内容物に対する異常免疫応答などが疾患の発症や維持に関わることが知られている。

IBDには従来栄養療法やステロイド,5-ASA,免疫調整薬などを用いた治療が中心であったが,2002年に炎症メディエーターであるTNFαそのものをターゲットとする抗体である静脈注射の抗TNFα抗体製剤が用いられるようになってから治療が大きく変化した。しかし一方で,抗TNFα抗体製剤を用いても長期寛解維持が達成されない症例が一定数存在する。
その後,投与法や免疫原生をなくすよう作製法を変えた抗TNFα抗体製剤が発売され,また,近年では,特に腸炎に関与する新たな分子をターゲットとした生物学的製剤や低分子化合物が次々と保険適用となり,難治のIBD患者に対する治療の幅が広がっている。UCではJAK,α4β7インテグリン,CDではIL-12/23p40など,腸管炎症に関わる分子を標的とした治療薬が用いられる。その標的分子の違いより個々の患者の病態に応じた使いわけがあって然るべきであり,今後は適切な治療薬の選択,使用に関する知見の蓄積が望まれる。
【解説】
飯島克則*,下平陽介 秋田大学消化器内科/神経内科 *教授