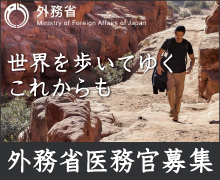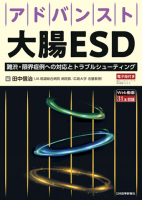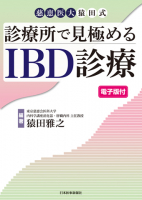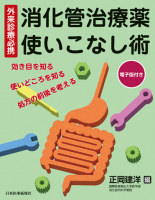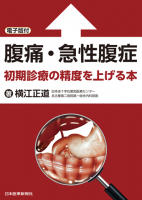お知らせ
ヘリコバクター・ピロリ感染症[私の治療]
ヘリコバクター・ピロリ(Helicobacter pylori)感染症は,幼少期に本菌が感染することによって生じ,萎縮性胃炎を引き起こす。本菌の持続感染は,胃・十二指腸潰瘍,胃MALTリンパ腫,免疫性(特発性)血小板減少性紫斑病(ITP)や胃癌の発症に関与することが報告されている。また,本菌の除菌治療により,胃・十二指腸潰瘍の再発抑制,胃MALTリンパ腫の寛解やITPの血小板数増加が期待でき,さらには胃癌の発症抑制効果も報告されている。
▶診断のポイント
H. pyloriの感染診断については,内視鏡検査を必要とする侵襲的検査法と,内視鏡検査を要さない非侵襲的検査法がある。侵襲的検査として,①迅速ウレアーゼ試験(RUT),②鏡検法,③培養法の3種類,非侵襲的検査として,④尿素呼気試験(UBT),⑤抗体測定法,⑥便中抗原測定法の3種類,計6種類の検査方法がある。除菌治療前の検査では,いずれの検査法を用いても診断精度に大きな差はないが,除菌後には菌体数が減少しているため,精度の高い除菌判定が必要である。日本ヘリコバクター学会による「H. pylori感染の診断と治療のガイドライン2016改訂版」1)では,除菌判定の検査法としてUBTとモノクローナル抗体を用いた便中ヘリコバクター・ピロリ抗原測定が推奨されている。

また,抗菌薬,プロトンポンプ阻害薬(PPI),カリウムイオン競合型アシッドブロッカー(P-CAB)など,H. pyloriに対する静菌作用を有する薬物が投与されている場合,除菌前後の感染診断の実施にあたっては,偽陰性の可能性を減らすために,これらの薬物投与を2週間以上中止することが望ましい。
▶私の治療方針・処方の組み立て方
保険適用の一次除菌治療法,二次除菌治療法は投薬方法が決められている。
一次除菌治療では,タケプロン®(ランソプラゾール)1回量30mg,オメプラール®(オメプラゾール)1回量20mg,パリエット®(ラベプラゾール)1回量10mg,ネキシウム®(エソメプラゾール)1回量20mg,タケキャブ®(ボノプラザン)1回量20mgのいずれか1種類と,クラリス®(クラリスロマイシン)1回量200mgもしくは400mg,アモリン®(アモキシシリン)1回量750mgの3剤を組み合わせ,1日2回,7日間服用する。
二次除菌治療では,クラリス®(クラリスロマイシン)をフラジール®(メトロニダゾール)1回量250mgに変更した3剤を組み合わせ,1日2回,7日間服用する。
なお,現在の保険診療では,アモリン®(アモキシシリン)がペニシリン系抗菌薬であるため,ペニシリンアレルギー患者や二次除菌不成功者,小児への除菌治療は行えない。
上記除菌治療後4週以降に除菌判定を行う。除菌判定は前述したように,UBTもしくは便中ヘリコバクター・ピロリ抗原測定がガイドラインで推奨されている。

残り917文字あります
会員登録頂くことで利用範囲が広がります。 » 会員登録する