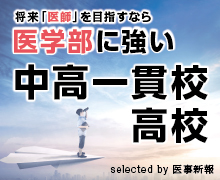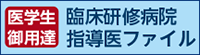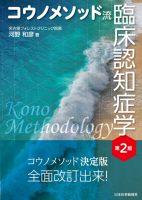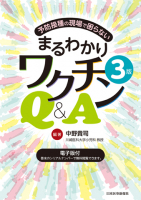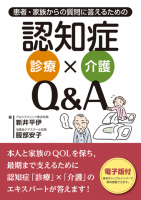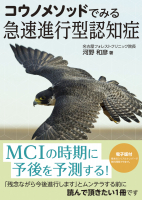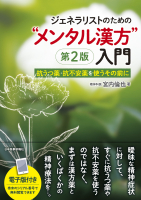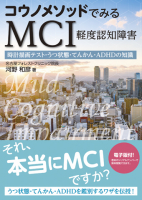お知らせ
東日本大震災被災者の嗜癖問題の状況
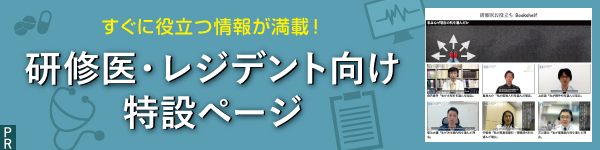
【Q】
多くの犠牲者を出した東日本大震災から,4年が経過しました。東北地方の被災者の飲酒,ギャンブルなどの嗜癖問題はどのような状況にあるのでしょうか。仮設住宅などで不自由な生活を長期に強いられ,様々な面でストレスの多い被災者にとって手軽なストレス解消法は飲酒やギャンブルになってしまうかもしれません。アルコールやパチンコなどにはまって,健康を害したり依存症になってしまう人が増えるのでないかと懸念します。国立病院機構久里浜医療センター・松下幸生先生のご教示をお願いします。【質問者】
杠 岳文:国立病院機構肥前精神医療センター院長
【A】

1995年の阪神・淡路大震災の際には,仮設住宅での孤独死が問題となり,誰にも看取られずに亡くなった方々の検死結果によると,そのほとんどが病死で,40~60歳代の男性では死因の3割程度をアルコール性肝疾患が占めたことから,被災地でのアルコール問題がクローズアップされました。しかし,阪神・淡路大震災後の酒類販売に関する調査では,災害後の住民の移動や販売店の減少を調整しても,激しく被災した地域では酒類販売量が有意に減少したという報告もあります。一方,新潟県中越地震に関連した調査では,被災地の男性におけるアルコール依存症や乱用の有病率の高さが報告されました。このように,国内の災害でもアルコール関連問題との関係を示唆する調査結果もみられます。
当院では他の施設と共同で研究班を組織して,東日本大震災が飲酒,睡眠薬の使用,ギャンブルなどにどのような影響を及ぼしたか調査しました。2012~13年に岩手県・宮城県の沿岸部および内陸部にお住まいの人々,さらに全国から無作為に抽出された一般住民の人々に協力して頂いて飲酒などの実態を調査するとともに定期的に岩手県や宮城県の被災地を訪問し,事例相談や研修などをさせて頂きました。
横断調査の結果,全国調査結果と比較して,岩手県・宮城県の沿岸部では全体的に飲酒率は低く,アルコール使用障害のスクリーニングテスト(The Alcohol Use Disorders Identification Test:AUDIT)で高得点の割合は全国調査の結果と差はありませんでした。しかし,習慣的に飲酒する人に限ると,男女ともAUDIT高得点の割合が被災地で高いことや沿岸部では震災による失業とAUDIT高得点が相関するなど,アルコール関連問題には二極化の傾向が示唆されました。
この調査では面接によって国際疾病分類 第10版(International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems 10th revision:ICD-10)のアルコール依存症の基準に該当するか否かを調べていますが,アルコール乱用や依存症の有病率は被災地と他の地域で有意差は認められませんでした。
一方,睡眠薬の使用は沿岸部の女性に多く,ギャンブル依存の傾向は沿岸部の男性に多いなど,飲酒以外の嗜癖関連行動の問題も被災地に多いことが示されました。
過去の研究は,アルコールや薬物といった物質依存・乱用は災害後に一過性に増加するとしています。研究班では岩手・宮城両県で調査に協力して頂いた人を対象に再調査を実施しておりますが,その結果は別の機会にご紹介できると思います。