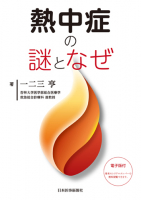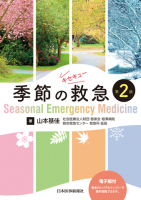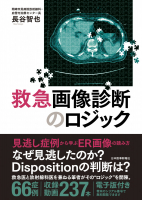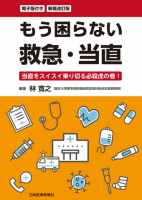お知らせ
新興感染症・再興感染症,輸入感染症[私の治療]
コロナ禍からポストコロナ時代となり,インバウンド需要が急速に高まる状況において,感染症リスクも上昇していると言える。公衆衛生上のリスク回避,ならびに予期せぬ治療失敗を引き起こさないためには,宿主因子として特殊な感染症を考える状況か否かを見きわめることが重要である。新興感染症・再興感染症ともに,わが国では輸入感染症として対応する場合が多いと考えられる。
▶病歴聴取のポイント
①渡航歴

特に海外渡航歴について問診を行うことは重要である。一般的に,先進国よりも開発途上国のほうが特殊な感染症リスクが高く,対応に難渋するケースも多いと考えられるが,近年のCOVID-19,エムポックスなど先進国においても公衆衛生上の問題となる感染症が定期的に発生している。また,同じ国においても,地域によって感染症リスクは大きく異なり,どこに,どれくらいの期間滞在していたのか,詳細な問診を行う必要がある。渡航地が確認できれば,ウェブサイト「厚生労働省検疫所(FORTH)」1)などで最新の情報を入手することが可能である。
②生活歴と曝露歴
生活歴として,ワクチン接種歴について確認することが重要である。日本国籍であっても,幼少期に長期海外居住歴がある場合などでは,本来接種されているはずのワクチンが未接種の場合も稀ではなく,免疫獲得がされていない場合がある。また,特に大きな問題となる感染症は,ヒト-ヒト感染が成立する感染症であり,周囲に同様の症状を呈するものがいなかったか,いわゆるシックコンタクトの確認が必要となる。さらに,食文化や性を含めた生活様式の多様化にも留意する必要がある。動物・昆虫咬傷を含め,アクティビティとして自然界への接触の有無,生食や非日常的な食事摂取の有無,無防備な性交渉の有無など,疾患を想定した効率的な問診が必要となる。
③潜伏期
多くの急性熱性疾患の潜伏期が14日までである一方,数カ月の潜伏期を経て発症する感染症や,持続感染する感染症もある。渡航歴や生活歴,曝露歴から想定される疾患を念頭に,潜伏期として矛盾がないか確認する必要がある。また,潜伏期から疾患が想定・除外される場合もある。
④緊急性の有無
①~③の問診から,直ちに対応が必要な感染症かどうか判断する。1類感染症のように重篤で生命に関わる疾患のほか,公衆衛生上,急ぎの対応が必要な疾患もある。普段から相談できる窓口を確認しておくとよい。

残り985文字あります
会員登録頂くことで利用範囲が広がります。 » 会員登録する