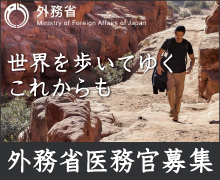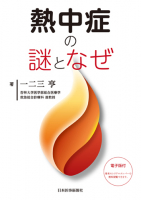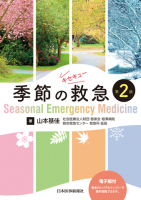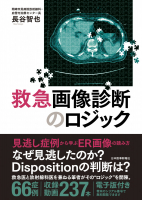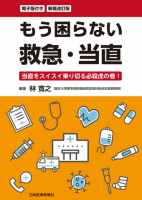お知らせ
薬物中毒[私の治療]
薬物中毒に対する治療においては,まずは全身管理と対症療法により全身を安定化させる。ついで,状況確認やトキシドローム(中毒の臨床症状)により病因物質を推定し,吸収阻害,排泄促進,解毒・拮抗薬の投与などを行う。トキシドロームにはオピオイド性,鎮静/催眠性,交感神経作動性,抗コリン性,コリン作動性などがある。
▶病歴聴取のポイント
病因物質の同定には受傷状況などの情報が重要である。残薬や容器は持参させる。抗精神病薬などの処方歴も確認する。
実臨床ではトキシドロームから病因物質を推定する。うつ病の治療歴がある患者が意識障害,痙攣,不整脈,散瞳を呈していれば,抗コリン性の三環系抗うつ薬の過剰摂取が疑われる。
▶バイタルサイン・身体診察のポイント
気道・呼吸・循環から診察に入り,生理的な安定化を図る。心電図所見が病因物質同定の手がかりになることもあるため,心電図モニタリングは必須である。三環系抗うつ薬,交感神経作動薬,循環作動薬などの中毒では心血管系の異常を生じる。痙攣の多くは全般発作で,全身の強直・間代性痙攣と意識消失を伴う。体温管理は環境要因だけではなく,病因物質による影響も考慮する。

残り1,515文字あります
会員登録頂くことで利用範囲が広がります。 » 会員登録する