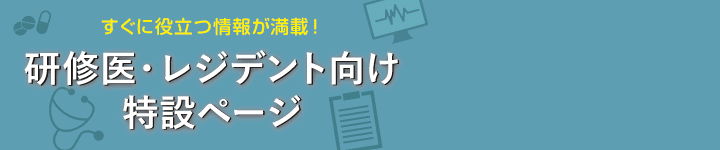お知らせ
遅い研修[炉辺閑話]
私は卒後8年目、大阪府立羽曳野病院呼吸集中治療室で1年間を過ごした。研修と言うには、いささか薹が立っていたが、それは苦手な呼吸器疾患の穴を埋めるためであった。
その1年で最も印象深かったのは、集中治療室主幹の木村謙太郎先生、筋萎縮性側索硬化症(ALS)のため入院されたSさんとの出会いである。40歳代でALSと診断されたSさんは、奥様とともに謙太郎先生の外来を訪ねた。「やがて、私は呼吸ができなくなる。その時がきたら人工呼吸を導入し、家で人工呼吸器とともに暮らせるようにしてほしい」。

私は彼の主治医となった。人工呼吸器が必要となる日が、すぐ目の前だったが、Sさんは、奥様と2人の息子さんと過ごすため、病院から車で30分の距離にあるご自宅への、週末の外泊を希望された。私は、その申し出に答えることができず、謙太郎先生を訪ねた。「いいですよ。彼も、奥様も覚悟の上だから」と、悩んでいる私が不思議そうな表情だった。何度目かの外泊の翌朝、私は挿管され、人工呼吸器につながれたSさんと対面した。ぎりぎり間に合ったのである。ホッとする間もなく気管切開をし、家で使用する小型の人工呼吸器に変更し、彼にあわせて設定を決めた。はたして、これで上手くいくか?私は動脈血液ガスを採取し、そのデータを謙太郎先生にみせた。先生はデータには目もくれず、Sさんの傍らにおもむき、「如何ですか?」と尋ねた。にっこり頷くSさんをみて、黙って自室に戻られた。
私は血液ガスのデータを屑籠に捨てた。Sさんはその後、望み通り、家族と人工呼吸器とともに暮らす生活に入られ、私は、生まれて初めて、在宅人工呼吸の患者さんの生活を支える訪問診療を経験した。隙間を埋めるためであった羽曳野病院での経験は、その後の人生を変えることになった。
いつのまにか、呼吸器内科を専門とした私は、木村先生に倣って「息切れ医者」と名乗り、多くの慢性呼吸不全の患者さんと出会い、開業した今も、Sさんのように「ご自宅で過ごすこと」を望む患者さんの生活をケアする日々を続けている。