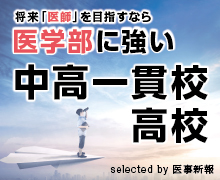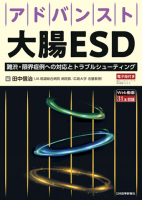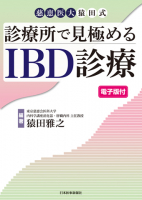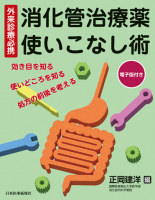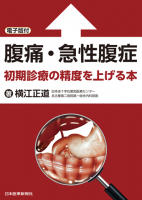お知らせ
消化器疾患に対する心身医学的アプローチ 過敏性腸症候群の診断と治療UPDATE [学術論文]
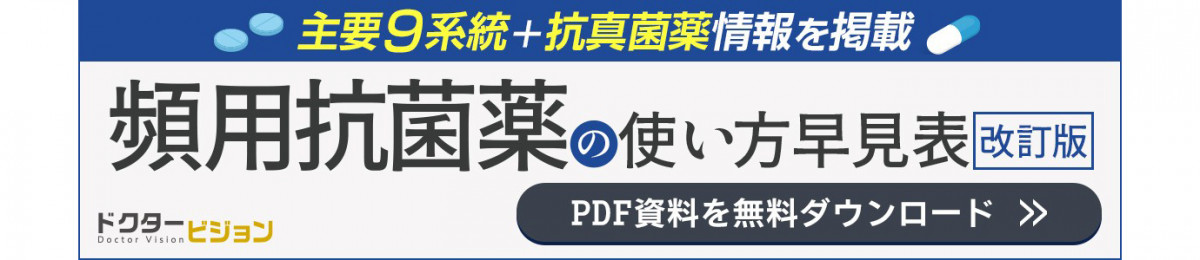
過敏性腸症候群(IBS)は,機能性消化管疾患の代表的疾患であり,一般人口において有病率が高く,生活の質(QOL)を障害する強い疾患である。近年,病態生理や治療に関する研究が進み,新たな知見が得られるようになった。また,2014年になり,日本消化器病学会から診療ガイドラインが発刊され,エビデンスに基づいた診療指針が提示された。本稿ではIBSの疫学,診断,病態生理,治療に関しての最新の知見について概説する。
1. 過敏性腸症候群(IBS)とは
過敏性腸症候群(irritable bowel syndrome:IBS)は,機能性消化管疾患の代表的疾患で,腹痛または腹部不快感とそれに関連した便通異常が慢性もしくは再発性に持続し,日常診療でみられる機会が多い。しかし,下部消化管内視鏡検査および病理組織学的検査などで診断が確定できるような器質的疾患とは異なり,検査で客観的異常をとらえにくい疾患であること,また,心理社会的ストレスなどを背景として,消化器症状以外にも様々な症状を訴えたり,内服治療を行ってもなかなか症状が改善せず,たびたび病院を受診することもあり,IBSの治療はとっつきにくいという印象を持っている先生方も少なくないかと思われる。また,致死的な疾患でないことも積極的治療をためらう要因の1つと考える。
しかし,最近のメタアナリシス1) によるとIBSの一般人口における有病率は10~12%と高頻度であり,また,生活の質(quality of life:QOL)を障害する強い疾患2) であることから,世界で病態解明や有効な治療に関しての研究が進められている。本邦でもIBSをテーマにした研究会や,学会シンポジウム,ワークショップが多く開催されるようになった。また,2014年4月には日本消化器病学会から,現在のIBSのエビデンスを集積して作成された「機能性消化管疾患診療ガイドライン2014─過敏性腸症候群(IBS)」が発表された3)。IBSの疫学,病態から診断,治療に至るまで,クリニカルクエスチョン(CQ)が設定され,エビデンスに基づいたステートメントが示されており,IBS診療の新たな道標として活用が期待される。
近年になり新たな治療薬が発売され,さらに,食事療法やプロバイオティクスに関しての新たなエビデンスも示されたことで,IBSの病態に合った,より有効な治療選択が可能となった。本稿では,最近のIBSの知見を交えて概説する。


残り6,087文字あります
会員登録頂くことで利用範囲が広がります。 » 会員登録する