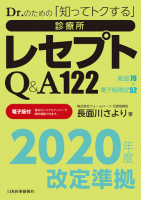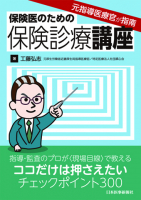お知らせ
■NEWS 地域包括医療病棟、内科疾患と外科疾患の評価に差異―入院外来分科会
診療報酬調査専門組織の入院・外来医療等の調査・評価分科会は7月17日、包括的な機能を担う入院医療を巡り議論した。2024年度診療報酬改定で新設された地域包括医療病棟については入棟患者の疾患別分析で、内科疾患は外科疾患よりも包括範囲に含まれる診療行為が多く、請求点数は低いことが判明。内科疾患の評価が外科疾患に比べて不利になっている可能性が示唆された。
地域包括医療病棟は包括評価の病棟であり、検査、画像診断、投薬、注射、処置などは原則、入院料に含まれる。入棟患者の疾患別分析をみると、包括範囲内の出来高換算点数は疾患ごとでばらつきがあり、特に誤嚥性肺炎、脳梗塞、尿路感染症などの内科疾患は包括内の出来高換算点数が高く、請求点数は低い傾向にあった。内科疾患は、検査・処置などを要する救急搬送患者や緊急入院患者が多いことが要因とみられる。診断群分類による分析では、緊急入院の割合が高い診断群や、出来高算定できる手術の実施割合が低い診断群の包括内の出来高換算点数が高いことも確認できた。

分析結果を踏まえ中野惠委員(健康保険組合連合会参与)は、「内科系と外科系が公平な評価になるための方法を考える必要がある。疾患ごとの医療資源投入量についてさらに分析すれば何か見えてくるのではないか」と追加分析を要請。津留英智委員(全日本病院協会常任理事)は、「外科系はある程度予定を組んで手術ができるが、内科系は明らかに救急搬送、緊急入院が多い。特に85歳以上の内科系症例は緊急入院が多く、この辺りをどう評価するかが課題だ」との見解を示した。
■地域包括ケア病棟は栄養管理の評価が論点に
会合では、地域包括ケア病棟における栄養管理の評価についても議論した。地ケア病棟は管理栄養士の配置が要件化されておらず、栄養管理に関する加算や管理料は入院料に包括する扱いとなっている。このため40床当たりの管理栄養士数は地域包括医療病棟や回復期リハビリテーション病棟などに比べると少なく、管理栄養士が病棟で業務に従事する時間も短い傾向にある。また、入院時栄養スクリーニングで低栄養リスク有りとなった患者の割合は地域包括医療病棟よりも低いが、厚生労働省は「適切に覚知されていない可能性がある」とみている。